ミスマッチ解消!ワークサンプルテストで人材を見極める方法と注意点
2025.07.14

「優秀だと思ったのに、入社後にスキル不足が判明した」
「本人の主張するスキルレベルと自社が求めるスキルレベルに乖離があった」
こんな経験はありませんか?
日本では少子高齢化による労働人口の減少や人材の流動化が進んでおり、自社に適した人材を見極めることへの重要性が高まっています。
候補者が自社にマッチしているかどうかを事前に見極める方法のひとつに、ワークサンプルテストがあります。
ワークサンプルテストは候補者の自社での業務遂行能力を見極める選考手法です。
この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
- ワークサンプルテストとはどのようなものか
- ワークサンプルテストが注目されるに至った背景
- ワークサンプルテストを導入する目的
- ワークサンプルテストの実施時期・実施パターン
- ワークサンプルテストの導入の流れ
- ワークサンプルテストを導入するメリット・デメリット
- ワークサンプルテストで採用を成功に導くポイント
- ワークサンプルテストの企業事例
ワークサンプルテストとは
ワークサンプルテストとは、選考を受けている候補者に対し、入社後に実際に就く業務を体験してもらう採用手法のひとつです。
採用選考中に行う体験入社、またはインターンシップといえばイメージしやすいかもしれません。
ワークサンプルテストを実施すれば、書類や面接では見極めにくい業務適性やスキルを事前に把握しやすくなります。
特にエンジニアや技術開発など、専門知識が必要な職種の採用で有効といわれています。
ワークサンプルテストが注目される背景
少子高齢化の影響で、現在の労働環境は売り手市場になっており、年々採用の難易度が上がっています。
採用難易度が高いということは、ただ採用活動を行うだけでは自社に適した人材を採用することが難しいということです。
ワークサンプルテストは仕事のパフォーマンスを予測する精度が高いことが報告されています。
ジョブ型雇用が主流の欧米ではワークサンプルテストが広く用いられており、米IT企業大手Google社でも導入されています。
これまでの日本は職務内容を限定せず、会社のニーズに合わせて従業員を配置するメンバーシップ型雇用が一般的でした。
しかし、近年は日本でも専門職採用の活発化により、仕事に人をつけるジョブ型雇用の導入が進んできています。
このような背景から、より自社の求める人材を見抜くための手法としてワークサンプルテストが注目されるようになりました。
ワークサンプルテストを導入する目的
ワークサンプルテストを導入する目的には以下のようなものがあります。
- 自社に適した人材の確保
- 採用ミスマッチの防止
- スキルレベルのチェック
それぞれについて下記で解説します。
自社に適した人材の確保
ワークサンプルテストを実施すれば、自社にマッチする優秀な人材の確保につながります。
書類や面接といった従来の採用手法だけでは、候補者の具体的なスキルや適性を判断することが困難です。
ワークサンプルテストを活用すれば、事前に候補者のスキルや適性が可視化されるため、自社に適した人材の確保につながります。
採用ミスマッチの防止
採用ミスマッチの軽減もワークサンプルテストの目的のひとつです。
離職の原因のひとつに、採用ミスマッチがあります。
実際に入社してみると、「思っていた業務内容や職場環境と違った」というのは早期離職によくあるケースです。
企業側がウェブサイトや説明会、面接などで業務内容や社風のことを説明しても、実際に働いてみないとわからないこともあります。
ワークサンプルテストは入社後に実際に就く仕事を体験してもらうため、ミスマッチを防ぐことにつながります。
また、実務に携わるだけでなく、会議に出席したり、従業員と一緒にランチをとったりすることで、自社の雰囲気を知ることができます。
スキルレベルのチェック
ワークサンプルテストは候補者のスキルレベルのチェックができます。
候補者のスキルレベルを面接や書類で確認しても、実務においてどの程度のレベルかはわかりません。
ワークサンプルテストで実際の仕事を体験してもらえば、自社の求めるスキルレベルに達しているかどうかをはかることができます。
ワークサンプルテストの実施時期と実施パターン

ワークサンプルテストは1次、2次面接を通過した候補者を対象に、最終面接の直前に行うというのが多いです。
また、ワークサンプルテストの実施期間としては数時間程度のものから一日かけて行うものまでがあります。
ワークサンプルテストの主な実施パターンは以下の3つです。
- 半日〜1日の体験入社(オフライン)
- 半日の体験入社(オンライン)
- 課題を提出後に従業員と意見交換 など
ワークサンプルテストの導入の流れ
ワークサンプルテストの導入の流れは以下のとおりです。
- 採用要件・ペルソナの設計
- 課題・評価基準の設計
- 課題の作成・実施方法の選定
それぞれ、順を追って解説します。
採用要件・ペルソナの設計
まず、自社がどのような人材を求めるのか、採用要件とターゲット像を明確にし、ペルソナを設計します。
ペルソナを設計したら、どのようスキルが必要なのか特定します。
課題・評価基準の設計
次に具体的な課題や評価基準を設計します。
ペルソナに必要なスキルを満たすためにはどのようなテストや課題を実施すべきか、どのように評価するのか、評価基準・合格基準はどこかなどを逆算して考えます。
課題内容の一貫性と客観性を担保するためにも、例えば下記のような項目を数字などの定量的な指標で設定します。
- 課題の完了度
- 正確性
- 効率性 など
課題の作成・実施方法の選定
必要なスキルを評価する課題を作成します。課題は候補者が入社後に実際に就く仕事の要素を含むように構成します。
具体的な課題の例は下記のとおりです。
- ITエンジニア:簡単なプログラミング修正、小規模なアプリケーション実装
- WEBデザイナー:既存デザインの改善提案、Webページのモックアップ作成
- 営業:提案資料作成+プレゼン、トークスクリプト作成、ロープレ
- マーケティング:簡単なアンケート分析、ペルソナ設定+施策立案 など
なお、課題を作成する際はオンラインなのかオフラインなのか、テスト形式、実施場所、使用ツールまで決めておきます。
テストの形式の例としては以下のようなものがあります。
- プレゼンテーション
- 課題提出
- 実技テスト
- グループワーク
- ロールプレイング など
このとき、評価すべき項目や候補者の負担、選考フローなども考慮して決めることが重要です。
ワークサンプルテストを導入するメリット

ワークサンプルテストを導入するメリットには以下のようなものがあります。
- 自社に適した人材を見極められる
- 採用面接を効率化でき、採用コストの削減につながる
- 入社後のミスマッチを軽減できる
- 入社への動機づけにつながる
それぞれについて下記で解説します。
自社に適した人材を見極められる
ワークサンプルテストは実際の業務に近い内容のテストを行うことで、書類や面接ではわからない、自社での業務遂行能力を評価できます。
そのため、ワークサンプルテストを実施すれば自社に適した人材を見極められるというメリットがあります。
採用面接を効率化でき、採用コストの削減につながる
ワークサンプルテストは候補者のスキルや実務での業務遂行能力を把握しやすくなります。
従来の選考方法では、面接のなかで候補者の内面とスキルを同時に評価しなくてはなりませんでした。
限られた時間内で多くのことを評価するというのは、面接官の負担も大きく、十分な判断が難しいものです。
ワークサンプルテストを面接と組み合わせれば、スキルや適性はワークサンプルテスト、仕事への価値観や志向性は面接、というように評価項目をわけることができます。
こうすることで、面接官は候補者の仕事への価値観といった内面を重視して選考することができ、採用精度が向上し、面接官の負担も少なくなります。
入社後のミスマッチを軽減できる
ワークサンプルテストを実施することで、企業は候補者の適性やスキルを正しく評価しやすくなります。
また、候補者も社風や業務内容を事前に把握できるため、ミスマッチが起きにくくなります。
入社への動機づけにつながる
ワークサンプルテストは候補者の入社への動機づけの効果もあります。
実際の業務を体験してもらったり、従業員とコミュニケーションを取ってもらったりすることで、自社の社風や魅力、業務内容を肌で感じてもらいやすくなります。
説明会や面接ではわかりづらい企業の魅力が伝われば、内定辞退も減り、入社への意欲が高まります。
ワークサンプルテストを導入するデメリット

ワークサンプルテストを導入するデメリットには以下のようなものがあります。
- 選考期間が長くなる
- 選考を辞退される可能性がある
- 担当者と現場の工数が増える
それぞれについて下記で解説します。
選考期間が長くなる
ワークサンプルテストのデメリットのひとつは選考期間が長くなることです。
選考期間が長くなると、候補者が途中で選考を辞退することがあります。
また、選考期間が長期化すれば、採用担当者の負担も増えます。
採用を効率化し、より良い人材を見出す目的でワークサンプルテストを導入したのに、候補者の離脱が増えてしまえば本末転倒です。
候補者の離脱を防ぐためにも、ワークサンプルテストを導入する際は、以下の点に注意することが大切です。
- 内定までどのくらいかかるのかを事前に伝えておく
- ワークサンプルテストを実施する背景や意義を伝える
- 上記2つのことをできるだけ選考の早い段階で伝える
選考を辞退される可能性がある
ワークサンプルテストは半日から1日程度かかります。
そのため、ワークサンプルテストがあること自体に負担を感じて選考を辞退するケースもあります。
ただし、このような候補者は自社への志望度が高くないとも考えられます。
そのため、採用したとしても内定辞退や早期離職にいたる可能性もあります。
ワークサンプルテストはミスマッチを防ぐ目的もあるため、選考辞退をされた場合は「事前にスクリーニングできた」と前向きに捉えましょう。
担当者と現場の工数が増える
ワークサンプルテストを導入すると課題の作成や確認作業が発生します。
また、候補者を現場で受け入れる場合は現場との調整やリソースが必要になり、工数が増えることになります。
ワークサンプルテストで採用を成功に導くポイント

ワークサンプルテストを実施して採用を成功に導くためのポイントをご紹介します。
- 評価項目を明確に定めておく
- 入社後に実際に就く業務と近い内容で実施する
- 役割外のパフォーマンスを予測しない
- フィードバックを必ず行う
- 多角的かつ総合的に判断する
- 知的財産権を遵守する
- バックグラウンドチェック・リファレンスチェックを併用する
それぞれについて下記で解説します。
評価項目を明確に定めておく
はじめに、評価項目を明確に定めておきます。
ワークサンプルテストの目的は候補者に自社の業務遂行能力があるかを見極め、ミスマッチを防ぐことです。
どのような人材がほしいのか、そのためにはどのような能力が必要で、どうすれば判断できるのかがわからなければ、せっかくのテストが無駄になってしまいます。
そのため、候補者の採用後の配属先に対して必要なスキルやレベルをヒアリングし、評価項目を定めておきましょう。
入社後に実際に就く業務と近い内容で実施する
ワークサンプルテストは候補者が入社後に実際に就く業務と近い内容で実施しましょう。
入社後の業務と近い内容を体験してもらうことで、候補者が入社後の仕事のイメージが湧きやすくなります。
また、企業側も候補者のスキルレベルをチェックできるため、ミスマッチを防ぐことにつながります。
つい、自社の良い部分を見せようと、普段の業務とは違った体験をさせたいと思うかもしれませんが、それでは意味がありません。
あくまで入社後のミスマッチ防止やスキルレベルのチェックが目的であると理解し、業務を選びましょう。
「泥臭い」と思われがちな業務が日常的にあるのであれば、そういった業務も体験してもらうと良いでしょう。
また、「優秀な人材を採用したいから」といって、必要以上に難易度を高めてはいけません。
テストの難易度が高すぎた結果、自社で活躍できそうな人材を逃してしまう恐れがあります。
「どのような内容が実務に近いのか」「どのぐらいのレベルであれば入社後にやっていけそうか」についても、現場にヒアリングしたうえで、評価項目を決めておきましょう。
できれば、現場の従業員に実際にテストを受けてもらい、所要時間や難易度について確認すると良いでしょう。
役割外のパフォーマンスを予測しない
ワークサンプルテストは自社に入社したあとの「特定の与えられた仕事を遂行する能力」を評価するものです。
文脈パフォーマンスを評価するものではありません。
文脈パフォーマンス(Contextual Performance)とは、組織の目標達成に直接的に貢献する職務遂行能力とは違い、組織全体の生産性や効率性を向上させ、円滑に進めるための行動をいいます。
具体的には、周りの同僚を助けたり、率先して協力をしたり、ルールを守ったりするという役割外の有益な行動のことをいいます。
文脈パフォーマンスは組織の活動にとって非常に重要な行動ですが、ワークサンプルテストでこれらの要素を評価することは困難です。
ワークサンプルテストはあくまで「特定の与えられた仕事を遂行する能力」を評価するものということを理解しておきましょう。
フィードバックを必ず行う

ワークサンプルテスト実施後は必ず候補者にフィードバックを行いましょう。
テストを受けることで自分の強みと弱みがわかれば、候補者にとって大きな学びになります。
もし採用に至らなかった場合も「丁寧に接してくれた」と好印象を抱くでしょう。
自社や自社の商品・サービスの評価が上がったり、ファンが増えたりするかもしれません。
採用に至った場合、企業側もどのような教育をすれば良いか事前に把握できるため、育成がスムーズになります。
多角的かつ総合的に判断する
ワークサンプルテストはあくまで判断材料のひとつです。
コミュニケーション能力や志向性、ストレス耐性などを測ることはできません。
また、ワークサンプルテストを実施したからといって、採用担当者のバイアスが完全に抑制されるわけではありません。
ワークサンプルテストを実施する際は他の選考手法と組み合わせ、多角的に評価し、総合的に判断することが重要です。
組み合わせの例としては以下のようなものがあります。
- 面接×ワークサンプルテストを
- 適性検査×ワークサンプルテスト
- グループワーク×ワークサンプルテスト など
知的財産権を遵守する
テストの内容が知的財産権を侵害していないかどうかも確認しましょう。
他社のテストを無断使用したり、著作物を模倣して使用したりしてはいけません。
求める人材やスキル、労働環境は企業によって異なります。
他社にフィットするテストを使っても、自社で正確に判断できるわけではありません。
他社のテストの情報は参考程度に留め、自社に適したオリジナルの内容を作成しましょう。
なお、テスト結果についても、採用活動の意思決定にのみ使用しましょう。
候補者が提出したアイデアや作品を、候補者の同意なしに採用以外の目的で使用してはいけません。
バックグラウンドチェック・リファレンスチェックを併用する
前述のとおり、ワークサンプルテストは自社での業務遂行能力を評価するものです。
例えば、前職での働きぶりや問題行動を起こしたことがないかなどは把握できません。
また、通常、応募書類を確認したうえでワークサンプルテストに進むことが多いでしょう。
しかし、提出された書類に虚偽があれば、どれだけワークサンプルテストの評価が良かったとしても、入社後にトラブルに発展する恐れもあります。
これらのトラブルを防ぐためにも、バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを併用し、通常の選考過程では見抜けない情報を補完し、多角的かつ総合的に評価することをおすすめします。
なお、バックグラウンドチェックとリファレンスチェックには以下の違いがあります。
- バックグラウンドチェック:候補者が主張する経歴に虚偽がないかを確認する
- リファレンスチェック:一緒に働いたことがある人にヒアリングを行い、前職での働きぶりについて確認する
ワークサンプルテストの企業事例
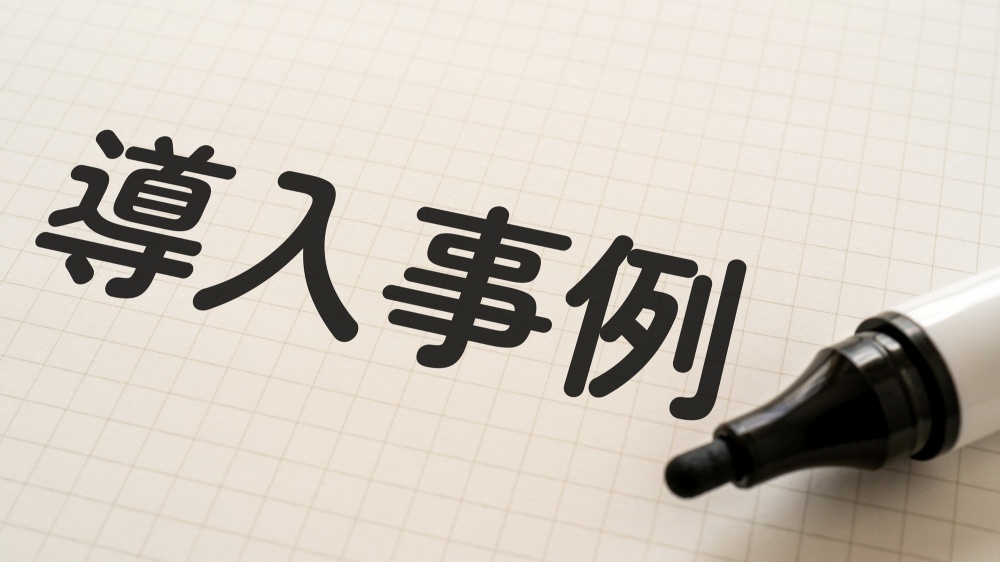
ここからは、実際に選考過程でワークサンプルテストを実施している2つの企業事例をご紹介します。
株式会社kubell(旧Chatwork)
株式会社Kubellは日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。
株式会社Kubellでは一部の部署・ポジションにおいて、面接プロセスのなかでワークサンプルテスト(体験入社・課題発表)を実施しています。
具体的には、二次面接でワークサンプルテストを実施し、同じ部署のメンバーの所感などを申し送りからチェックし、最終面接で確認します。
株式会社Kubell(旧チャットワーク)キャリア採用
https://www.kubell.com/recruit/career/
株式会社ログラス
株式会社ログラスは、経営管理クラウド「Loglass」を開発・提供しています。
ログラスでは、カジュアル面談や面接以外にワークサンプルテスト(実技試験)があり、職種ごとに以下のような試験を行っています。
セールス:ロープレ
エンジニア:コーディングテスト
マーケティング:ケース面接 など
株式会社ログラス採用サイト
https://www.loglass.co.jp/recruit
まとめ
ワークサンプルテストは候補者に入社後に実際に就く業務に取り組んでもらい、職務遂行能力を見極める採用手法です。
しかし、ワークサンプルテストだけでは職務遂行能力以外の能力をはかることはできません。
そのため、他の選考手法と組み合わせ、多角的かつ総合的に評価することが重要です。
例えば、前職での働きぶりや実績、評価、人柄をいったものはワークサンプルテストでは評価が難しいといえます。
これらの情報を補完し、採用精度を向上させるためにはバックグラウンドチェックやリファレンスチェックの併用がおすすめです。
ワークサンプルテストと併用することで、候補者の職務遂行能力だけでなく、人柄や実績、前職での働きぶりを客観的な視点で評価できるため、採用精度の向上につながります。
レキシルは経験豊富な調査会社のクオリティをリーズナブルな価格でご提供しています。
候補者のスキルや人柄や実績、働きぶりなどを多角的に評価したいとお考えの方はぜひご検討ください。

