ワークエンゲージメントとは?採用担当者が知るべき定義と施策
2025.10.22

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対してやりがいを感じ、ポジティブで充実した心理状態を指します。
「社員のパフォーマンスが上がらない」
「優秀な人材が定着しない」
これらの問題はワークエンゲージメントを高めることで解決につながる可能性があります。
本記事では、採用担当者が知っておくべきワークエンゲージメントの定義から、ワークエンゲージメントを高めるメリット、採用活動と連動させることでワークエンゲージメントを土台から高めるための具体的な施策を徹底解説します。
ワークエンゲージメントとは
ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対し、ポジティブで充実した心理状態にあることを指す言葉です。
単なる「やる気」や「熱心さ」ではなく、仕事から活力を得て、前向きに取り組んでいる状態です。
具体的には以下の3つの要素が満たされている心理状態のことをいいます。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 活力(Vigor) | 仕事に対してエネルギーに満ち溢れ、困難にも立ち向かえる精神的なタフさや高いレジリエンス(回復力)がある状態 |
| 熱意(Dedication) | 仕事に積極的に関与し、意義や価値を感じ、誇りを持っている状態 |
| 没頭(Absorption) | 仕事にのめりこみ、幸福感や時間が早く経つ感覚を得ている状態 |
ワークエンゲージメントはオランダのユトレヒト大学のSchaufeli(シャウフェリ)博士らが2002年に提唱した概念で、厚生労働省では「働きがい」とも表現しています。
従来の「バーンアウト(燃え尽き症候群)」研究の対極にあるものとして定義されています。
参考:厚生労働省「令和元年版労働経済の分析(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-2.pdf)」※1
ワークエンゲージメントが注目される背景
ワークエンゲージメントが注目されるようになった背景には、少子高齢化による労働人口減少と人材の流動化が挙げられます。
人手不足の状況のなかで、企業が競争力を維持するためには、一人ひとりの従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ることが不可欠です。
また、終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化により、従業員の主体性やモチベーションを維持することが従業員のメンタルヘルスや企業の持続的な成長に直結するようになりました。
このような背景から、優秀な人材に長く活躍してもらうためにもワークエンゲージメントが注目されるようになりました。
従業員エンゲージメントや従業員満足度(ES)との違い
との違い.jpg)
ワークエンゲージメントと間違われやすい言葉に、従業員エンゲージメントや従業員満足度(ES)があります。
それぞれについて、ワークエンゲージメントとの違いを整理しておきましょう。
従業員エンゲージメントとの違い
従業員エンゲージメントとは、組織エンゲージメントともいい、会社(組織)に対する愛着心や貢献意欲を指します。
従業員エンゲージメントは双方向の結びつきや関係性を重視する概念です。
従業員エンゲージメントが高い従業員は仕事に限らず、所属する組織や会社に対して強い愛着と自発的貢献意欲を持っています。
一方、ワークエンゲージメントは仕事そのものに対するポジティブで充実した心理状態をいい、仕事そのものから活力を得ている状態です。
一般的に、ワークエンゲージメントが高くなることで、結果として会社へのエンゲージメントも高まることが多いといわれています。
従業員満足度(ES)との違い
ワークエンゲージメントと類似する概念として従業員満足度(ES)があります。
両者には以下のような違いがあります。
- ワークエンゲージメント:「仕事から活力を得て積極的に貢献したい」という能動的な状態。
- 従業員満足度(ES):「給与、人間関係、労働環境などに不満がない」という受動的な状態であり会社との関係性を重視した状態。
従業員満足度は受動的な状態です。そのため、従業員満足度を高めたからといって必ずしも生産性向上に繋がるとは限りません。
しかし、ワークエンゲージメントは貢献意欲と直結しているため、ワークエンゲージメントを高めることは生産性向上につながるといえるでしょう。
ワークエンゲージメントと似た概念との関係性
ワークエンゲージメントを理解するには、その対極や混同されやすい概念を知ることも大切です。
ワークエンゲージメントと混同されやすい概念や対極となる概念には以下のようなものがあります。
- バーンアウト
- ワーカホリズム
- リラックス
それぞれについて下記で解説します。
バーンアウト
バーンアウト(燃え尽き症候群)は、ワークエンゲージメントの対極にある状態です。
仕事への活力を失っているため、活動水準が低く、仕事に対して否定的な心理状態を指します。
ワーカホリズム
ワーカホリズム(仕事中毒)は、活動水準が高く、仕事に強迫的に駆り立てられている状態です。
積極的に仕事に取り組んでいるわけではなく、「仕事をしなければならない」という否定的な感情に囚われている状態です。
仕事に没頭しているという点ではワークエンゲージメントと共通しているといえるかもしれません。
しかし、ワークエンゲージメントはポジティブな状態である一方、ワーカホリズムはネガティブな状態という点においては違いがあります。
リラックス
リラックスは職務満足感ともいい、職場環境や組織、仕事での自分の役割などに対してポジティブで満足度が高い状態をいいます。
仕事や組織に対して肯定的である点はワークエンゲージメントと共通しています。
しかし、活動水準が低く、仕事にエネルギーを注げていない状態である点でワークエンゲージメントと違いがあります。
ワークエンゲージメントを高めるメリット

ワークエンゲージメントを高めることで得られるメリットには以下のようなものがあります。
- 生産性の向上とパフォーマンスの改善
- メンタルヘルスの向上
- 離職率の低下と人材定着
- 顧客満足度の向上
- 組織へのコミットメント向上
それぞれについて下記で解説します。
生産性の向上とパフォーマンスの改善
ワークエンゲージメントを高めると、従業員が自発的・意欲的になることが期待できます。
従業員が自発的、意欲的に業務に取り組むことで、従業員自身の創造性や問題解決能力が高くなり、結果的に高い生産性を発揮することが期待できます。
メンタルヘルスの向上
厚生労働省の「令和元年版労働経済の分析」によると、「ワークエンゲージメントが高い従業員はストレスや疲労を感じにくい」という結果が出ています。
そのため、ワークエンゲージメントを高めることが従業員のメンタルヘルスを良好に保ち、精神的なストレスを軽減する効果が期待できます。
参考:厚生労働省「令和元年版労働経済の分析(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-2.pdf)」※1
離職率の低下と人材定着
ワークエンゲージメントが高い従業員は仕事に対してやりがいやポジティブな感情を持っています。
そのため、「辞めたい」と考える従業員が減り、優秀な人材の定着率が向上します。
厚生労働省の「令和元年版労働経済の分析」においても、ワークエンゲージメントが高いことで新入社員の定着率や従業員の離職率が改善したという結果が出ています。
参考:厚生労働省「令和元年版労働経済の分析(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-2.pdf)」※1
顧客満足度の向上
従業員のワークエンゲージメントを高めることは間接的に顧客満足度の向上にもつながります。
ワークエンゲージメントを高めることで、従業員一人ひとりが意欲的に仕事に取り組むようになり、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
その結果、自社商品や顧客への対応の質が向上し、結果として顧客満足度(CS)が向上しやすくなります。
組織へのコミットメント向上
ワークエンゲージメントが高まると、仕事だけでなく、周りの従業員や組織全体に対してポジティブな感情が生まれます。
その結果、職務に対する満足度や組織への貢献意欲が高まることが期待できます。
ワークエンゲージメントの尺度と測定方法

ワークエンゲージメントを効果的に高めるには、まず現状を定量的に把握することが必要です。
ワークエンゲージメントを定量的に測定するためにも、国際的に信頼性が高い代表的な3つの尺度を紹介します。
- UWES(Utrecht Work Engagement Scales)
- MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)
- OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)
それぞれについて下記で解説します。
UWES(Utrecht Work Engagement Scales)
UWES(Utrecht Work Engagement Scales)はワークエンゲージメント研究で最も広く用いられる代表的な尺度です。
「活力」「熱意」「没頭」の3つの尺度について17項目の質問に回答する形でスコアを算出します。
17項目のほかや9項目や3項目の短縮版もあります。
なお、日本国内では日本版UWESが用いられることもあります。こちらは9項目の質問に回答する短縮版です。
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)もワークエンゲージメントの測定方法のひとつです。
MBI-GSはワークエンゲージメントそのものではなく、その対極にあるバーンアウトを測定し、間接的にエンゲージメントの高低を判断します。
MBI-GSでは、下記の計16項目の質問について得られた結果からバーンアウトかどうかを測定します。
- 消耗感(疲労感) 5項目
- 冷笑的態度(シニシズム) 5項目
- 職務効力感 6項目
得られた結果が低ければワークエンゲージメントが高く、結果が高ければワークエンゲージメントが低いと判断します。
OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)
MBI-GSと同様、バーンアウトを測定し、間接的にワークエンゲージメントを判断する測定方法です。
MBI-GSと異なるのは、疲弊と離脱という2つの因子で状態を評価するという点です。
この結果が高ければワークエンゲージメントが低い、結果が低ければワークエンゲージメントが高いと判断されます。
ワークエンゲージメントを高めるために必要な要素
ワークエンゲージメントを高めるためには、その仕組みを把握する必要があります。
ワークエンゲージメントのメカニズムとして認知されている考え方に、仕事の要求度―資源モデル(JD-Rモデル)があります。
仕事の要求度―資源モデル(JD-Rモデル)では、「仕事の資源」「個人の資源」の2つの要素が相互に作用することでワークエンゲージメントが高まるとされています。
| 要素 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 個人の資源 | 個人が持つポジティブな心理的特性 | ・自分ならできるという自信 ・仕事に対する楽観性 ・レジリエンス(困難に屈せず、乗り越える対処力) ・希望(目標に向かって粘り強く取り組むこと) |
| 仕事の資源 | 仕事の目標達成やストレスの軽減を助ける、職場環境や組織によって提供される資源 | ・上司のサポート・コーチング ・正当な評価・フィードバック ・裁量の範囲 ・雇用の安定性・キャリア開発 |
ワークエンゲージメントを高める方法(個人の資源)
.jpg)
個人の資源とは、個人が持つポジティブな心理的特性を指します。
個人が持つポジティブな心理的特性、個人が持つ能力やスキルを向上させ、意欲を高めることでワークエンゲージメントの向上に寄与します。
具体的な方法について下記で解説します。
タイムマネジメントやコミュニケーションスキルの向上
個人の資源を充実させる方法のひとつにタイムマネジメントやコミュニケーションスキルの向上があります。
タイムマネジメントスキルを向上させることで、限られた時間のなかで生産性を高めることにつながります。
具体的には以下のようなものがあります。
業務における3M(ムリ・ムダ・ムラ)を洗い出し、無駄な作業を極力減らす
ITツールの導入により業務効率化を図る など
コミュニケーションスキルを向上させることも個人の資源を充実させる方法として効果的です。
従業員一人ひとりのコミュニケーション能力が向上すれば、人間関係が円滑になり、仕事へのストレスを減らす効果が期待できます。
ジョブ・クラフティングの実施
ジョブ・クラフティング(Job Crafting)も個人の資源を充実させる方法として有効です。
ジョブ・クラフティングとは、従業員一人ひとりが仕事への認識を主体的に捉え、行動するように修正することをいいます。
「やらされている仕事」から「仕事に主体的に取り組んでいる」という認識に変わることで、仕事へのやりがいを高まることが期待できます。
心理的ストレスの軽減
仕事へのモチベーションや主体性ばかりを重視すると、目標に到達しなかった際にストレスを感じ、心身のバランスを崩し、ワークエンゲージメントが低下する恐れがあります。
そのため、従業員の心理的ストレスを軽減することは個人の資質を充実させることも重要です。
従業員の心理的ストレス軽減策としては以下のような方法があります。
- EAP(従業員支援プログラム:Employee Assistance Program)
- ラインケア(上司が部下の変化にいち早く気づき、ストレス改善を行う)
- 相談窓口の設置
- 産業医やカウンセラーによるカウンセリング
- 定期的なストレスチェックの実施
- 休憩時などに運動の時間を設ける など
ワークエンゲージメントを高める方法(仕事の資源)
.jpg)
仕事の資源とは、組織の仕組みや環境を整えることで、従業員をサポートし、活力を引き出す施策です。
具体的な方法について下記で解説します。
適切なフィードバック・評価制度の見直し
従業員に対して適切にフィードバックを行い、適切に評価することは仕事の資源を充実させる効果的な方法です。
自分の業務が適切に評価されていなければ、やりがいを感じにくくなり、主体性も低下してしまいます。
「自分の貢献が正当に評価されている」と従業員が感じられる仕組みを整備し、納得感のあるフィードバックや評価ができるように制度の見直しを行いましょう。
適性に合った業務・ポジションを与える
従業員の適正やスキルに合った業務や配置を行うことで、「自分の能力が組織に貢献できている」という自信につながります。
裁量権を適切に付与することで、「主体的に取り組んでいる」という感覚が従業員に生まれます。
また、業務量を適切に保つことも重要です。
業務量が多すぎるとワーカホリックやバーンアウト状態に陥る可能性もあります。
一方、業務量が少なすぎると仕事に対してやりがいを感じにくくなってしまいます。
1on1で上司が部下の現状を定期的に把握し、業務量を適切にコントロールすることが大切です。
コーチング力の向上・サポート体制の充実
従業員のモチベーションや意欲は上司とのコミュニケーションの在り方でも左右されます。
管理職向けのコーチング研修などを実施し、部下の自律的な成長を促すスキルや従業員の能力を引き出すスキルを向上させると良いでしょう。
また、心理的安全性の高い組織作りや困ったときに助け合える風土・仕組みを作ることも大切です。
どのようなサポートがあれば良いかわからない場合は思いやり行動向上プログラムを参考にしてみると良いでしょう。
参考:思いやり行動向上プログラム実施マニュアル│島津明人研究室(https://hp3.jp/wp-content/uploads/2019/06/05.pdf)※2
柔軟な働き方ができる環境整備
リモートワークやフレックスタイム制度の導入など、柔軟な働き方の導入もワークエンゲージメントを高める方法のひとつといえます。
病気やけが、出産、育児、介護など、様々なイベントと両立しながらキャリアを築けることが可能になれば、従業員のモチベーションも向上しやすくなります。
また、有給休暇を取得しやすくする取り組みも強化すれば、よりワークライフバランスが充実し、従業員がメンタルヘルスを維持しやすくなり、ワークエンゲージメントの向上にもつながります。
キャリアパスの明確化とキャリア開発の機会の提供
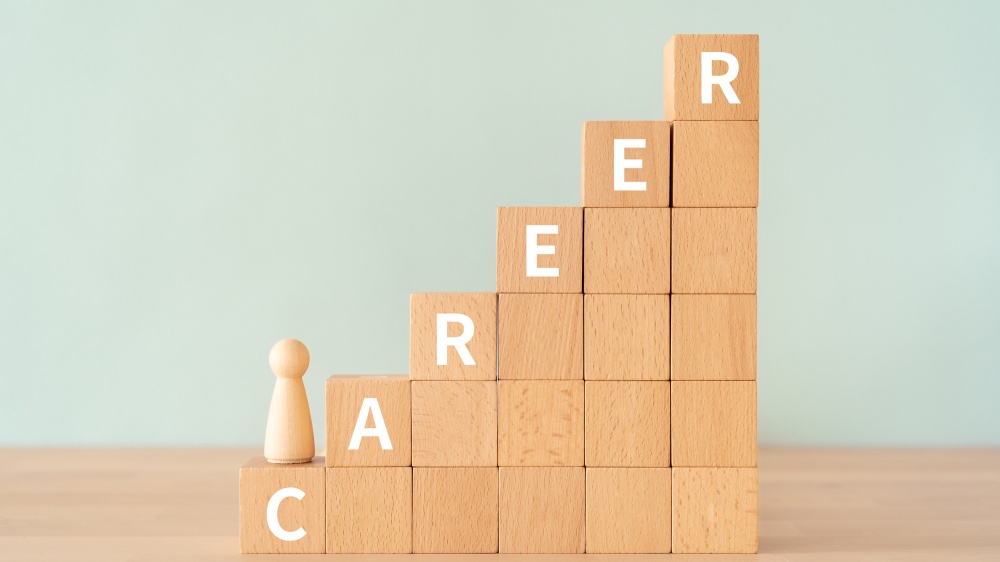
キャリアパスが明確になれば、仕事を通じて自分がどのように成長できるのかが見通せるようになります。
その結果、どのようなスキルを身につければいいか、どのように仕事に向き合えばいいかが明確になり、仕事へのモチベーションが高まり、主体的に業務に取り組むようになります。
キャリアパスを明確にするだけでなく、キャリア開発やスキルアップの機会を与えることも大切です。
キャリアパスが明確になり、スキルアップ・キャリア開発の機会が提供されれば、より前向きに仕事に取り組めるようになり、エンゲージメントが向上します。
具体的な方法としてはスキルアップ・キャリア開発につながる研修制度や社内公募制度の導入などがあります。
オフィス環境の整備
どれだけサポート体制を整備しても、オフィスが不潔であったり、暗かったりすれば、前向きな気持ちを維持することは難しくなります。
ワークエンゲージメントを高めるためには、清掃の徹底や空調の整備を徹底し、明るく、清潔な職場環境作りを徹底しましょう。
職場環境を整備することは業務効率化の側面でも効果的です。
動線を確保し、従業員が業務に取り組みやすい環境作りを整えましょう。
「個人の資源」と「仕事の資源」のどちらも重要
ここまで解説したとおり、ワークエンゲージメントを高めるには、個人の資源と仕事の資源、双方の資源をバランス良く高めることが大切です。
特に人事採用担当の方は「仕事の資源」における環境整備や制度の見直しにおいて、重要な役割を担います。
まずは自分の所属する部門をチェックし、環境整備や制度の見直しなどを試みてみると良いでしょう。
ワークエンゲージメントを高める際の注意点

ワークエンゲージメントを高める施策を効果的に進めるためには留意すべき点があります。
- 測定したスコアは属性別に考察する
- 従業員の負担にならないように注意する
- 目的を明確にし、長期的な視点で取り組む
- 採用段階でミスマッチを防いでおく
それぞれについて下記で解説します。
測定したスコアは属性別に考察する
ワークエンゲージメントは世界中で測定され、用いられています。しかし、その結果や傾向は国民性や文化によって異なります。
例えば、日本は海外と比較してワークエンゲージメントが低く出る傾向があることもわかっています。
測定したスコアは部署全体や全社平均だけでなく、部署や年代、ポジション、職種といった属性別に分析し、その特徴や傾向、課題の原因を特定することが重要です。
スコアが低い場合も一律の対応ではなく、個別に原因を分析し、その属性に合った施策を行うことも大切です。
従業員の負担にならないように注意する
調査の回答やエンゲージメント施策が従業員にとってノルマや負担にならないよう注意しましょう。
調査の頻度が多かったり、回答に時間がかかったりすると、正確なデータが得られにくくなる恐れがあります。
適切に調査を行うためにも、従業員の負担を軽減し、心理的安全性を確保したうえで、自発的な参加を促すことが大切です。
目的を明確にし、長期的な視点で取り組む
ワークエンゲージメントの測定や向上に取り組む際は、目的を明確にすることが大切です。
ワークエンゲージメントの測定や調査の目的、重要性を従業員に伝えないまま調査を行うと、会社に対する不信感が募り、正確な回答が得られにくくなります。
また、ワークエンゲージメントの向上は制度や組織風土の変革を伴うものです。
短期的な結果を求めてはいけません。
長期的な視点かつ継続的に取り組み、PDCAを回していくことが重要です。
調査結果が出たら必ず従業員に見える形で共有し、改善策を進めていくことが大切です。
採用段階でミスマッチを防いでおく
ワークエンゲージメントを高めるためには入社前にミスマッチを防いでおくことは非常に重要です。
企業のカルチャーや仕事内容、上司の期待値と、候補者の価値観やスキルが合っているかを採用段階で正確に見極めることは、ワークエンゲージメントを高める土台となります。
しかし、候補者の主張する経歴やスキルに虚偽があれば、採用ミスマッチが起き、その後の施策に影響をおよぼす恐れがあります。
採用活動の際はバックグラウンドチェックやリファレンスチェックを併用し、候補者の情報を多角的に評価することが大切です。
まとめ
ワークエンゲージメントは、企業が持続的に成長し、人材競争に打ち勝つための最重要指標です。
ここで解説した内容を参考に、「仕事の資源」と「個人の資源」を充実させ、従業員が活力を持ち、業務に没頭できるポジティブな環境を整備しましょう。
特に採用時のミスマッチを防ぐことはその後のワークエンゲージメント施策の土台となります。
ミスマッチ防止と定着率向上のためにも、採用プロセスにバックグラウンドチェックやリファレンスチェックを組み込むことをご検討ください。
※1 厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」
※2 思いやり行動向上プログラム実施マニュアル│島津明人研究室

