タレントマネジメントとは?導入目的と進め方、成功に導くポイント
2025.03.24

タレントマネジメントとは、従業員の才能(Talent)を一元管理し、教育、育成、適切な人員配置に活かすためのマネジメント手法です。
タレントマネジメントは適切に行わなければ十分な効果が得られないばかりか、生産性の低下や早期離職を招く恐れがあります。
この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
- タレントマネジメントとはどのようなものか
- タレントマネジメントの導入方法
- タレントマネジメントの導入で期待できる効果
- タレントマネジメントを成功に導くポイント
タレントマネジメントとは
タレントマネジメント(=Talent Management)とは、従業員が持つ能力や個性といった情報を経営資本として捉え、組織のパフォーマンスを最大限に高めるために組織横断的に行う人材マネジメント手法です。
米国コンサルファームマッキンゼー・アンド・カンパニーが「War for talent(人材育成競争)」を刊行したことで、世に広がりました。
タレントマネジメントの定義は人材マネジメント協会「SHRM」と、人材開発センター「ATD」(旧称:米国人材開発協会「ASTD」)の2つが著名なものとなります。
SHRM(全米人材マネジメント協会)での定義
人材の採用、選抜、適材適所、リーダーの育成・開発、評価、報酬、後継者養成等の人材マネジメントのプロセス改善を通して、職場の生産性を改善し、必要なスキルを持つ人材の意欲を増進させ、現在と将来のビジネスニーズの違いを見極め、優秀人材の維持、能力開発を統合的、戦略的に進める取り組みやシステムデザインを導入すること。
参考:SHAM 2006年度版タレントマネジメント調査報告書
ASTD(米国人材開発機構)での定義
仕事の目標達成に必要な人材の採用、人材開発、適材適所を実現し、仕事をスムースに進めるため、職場風土(Culture)、仕事に対する真剣な取り組み(Engagement)、能力開発(Capability)、人材補強/支援部隊の強化(Capacity)の4つの視点から、実現しようとする短期的/長期的、ホリスティックな取り組みである。
参考:ASTD 2008国際会議 参加報告
それぞれ、表現は違いますが、人材の採用や育成、適材適所に取り組むことで、従業員の能力やスキル、エンゲージメントを高め、組織の生産性を改善するための戦略的かつ中長期的な取り組みであることが読み取れます。
なお、タレントマネジメントの対象となるのは正社員だけでなくパートやアルバイトなどの非正規従業員も含む全従業員になります。
タレントマネジメントが注目される背景

タレントマネジメントが注目されるようになった背景には主に以下の4つがあります。
- 労働人口の減少
- 働き方の多様化
- ITの進化
- 事業環境の変化
それぞれについて下記で解説します。
労働人口の減少
日本は少子高齢化が長期化しており、労働人口の減少による人手不足が進行しています。
そのため、従来のように「新卒を大量に採用し、時間とコストをかけて育成する」といった手法が難しくなっています。
企業が存続し続けるためにも「人を増やして育てる」から「既存の従業員の生産性を上げる」という意識にシフトする必要があるのです。
働き方の多様化
最近ではリモートワークやフレックスタイム制など働き方の多様化やワークライフバランスを重視する働き方の需要が高まっています。
また、厚労省が推進する働き方改革においても、「長時間労働の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」などの実現を目指すとしています。
長時間労働の是正や柔軟な働き方により、労働時間が減少すると、同じ仕事をより効率よくこなさなければなりません。
その結果、労働者一人ひとりの生産性向上が求められるようになり、タレントマネジメントが注目されるようになりました。
参考:厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html)」※1
ITの進化
AIやITテクノロジーの進歩により、様々な分野において人間の感覚的なものではなく、数値化・定量化ができるようになりました。
人事・採用分野においても、クラウド・ビッグデータ分析や最先端のAI技術などにより、HRテックが活用されるようになりました。
HRテックとはHuman Resource(人材資源)テックの略称で、タレントマネジメントを支えるIT技術になります。
HRテックの普及により、タレントマネジメントの導入が容易になったことも、急速に拡大した要因と言えます。
事業環境の変化
企業を取り巻く環境は急速に変化しています。
前述のとおり、日本では労働人口の減少が進んでいます。
また、近年、企業の成長戦略として、M&Aや組織再編成が活発化しています。
プロジェクト体制で業務を進めるケースも増え、業務の掛け持ちや部署の横断なども頻繁に行われるようになりました。
このような背景から、人的資本を管理し、効果的に活用することが重要視されるようになりました。
タレントマネジメントを導入する目的

タレントマネジメントを導入する主な目的には以下のようなものがあります
- 自社の未来を担う人材の調達
- 人材育成・定着
- 適材適所の人員配置
それぞれについて下記で解説します。
自社の未来を担う人材の調達
米コンサルファームのマッキンゼー・アンド・カンパニーの提唱する「War for talent(人材育成競争)」にいより、企業にとって優秀な人材の育成が非常に重要であることが認識されるようになりました。
タレントマネジメントを導入することで、従業員一人ひとりの能力やスキルを把握できるようになります。
これにより、企業が目指す未来に向け、適切な研修を実施したり、新しいポジションに任命したりすることができるようになります。
人材育成・定着
適切な人材を確保し、長く定着してもらうことは企業存続のためにも重要です。
タレントマネジメントを導入することで、企業経営目標を達成するために必要な人員配置や人材の能力開発を効率的に実行することができます。
適材適所の人員配置
限られた労働力を最大限に活かすためには、従業員一人ひとりが自分の持つ能力を十分に発揮することが重要です。
タレントマネジメント導入により、従業員の能力を可視化・数値化することで、適材適所の人員配置が可能になります。
経営戦略の実現と継続的な成長が最大の目的
タレントマネジメント導入の最大の目的は経営戦略の実現と継続的な成長です。
事業拡大、売上や利益向上など、企業によって経営目標は異なります。
これらの目標に対し、人材調達・適材適所の人員配置・人材育成といった側面からアプローチし、実現することがタレントマネジメントの最大の目的です。
【企業側】タレントマネジメントの導入で期待できる効果

タレントマネジメントを導入することで企業側が得られるメリットは以下です。
- 中長期的な人材育成
- 適材適所の人員配置
- 業績や生産性の向上
- 採用コストの削減
それぞれについて下記で解説します。
中長期的な人材育成
タレントマネジメントにより、従業員一人ひとりの適性や能力可視化できれば、的確な育成が実現できます。
これにより、人材を効率的に育成することができます。
また、人材育成データを蓄積することで、新たな育成プランの立案や引継ぎも効率的に行えるようになります。
適材適所の人員配置
従業員一人ひとりの能力や特性に合ったマネジメントを行うことで、人材の持つ能力を最大限に生かした人員配置が可能になります。
また、人材の情報を一元管理することで、離職者が出たときも空いたポストに適した人材がいるかどうかを速やかに確認することができます。
業績や生産性の向上
従業員のスキルや個性に合った配置を行うことで、従業員のパフォーマンスが引き出すことができます。
従業員一人ひとりのパフォーマンスが向上すれば、組織全体のパフォーマンスの底上げにつながります。
組織全体のパフォーマンス向上し、生産性が上がれば、企業の業績向上や成長につながります。
採用コストの削減
タレントマネジメントは社内の人材情報を一元管理し、適材適所に配置します。
外部ではなく、社内の人材を有効に活用するため、採用コストの削減につながります。
新たに人を採用するより、社内で人材を異動させるほうが職場に馴染むのも早いため、育成コストの削減にも有効です。
外部から人材を採用する際も、どのような人材が足りないかが可視化できるため、ミスマッチが少なくなります。
【従業員側】タレントマネジメントの導入で期待できる効果
タレントマネジメントの導入は従業員にとってもメリットがあります。
従業員側が得られるメリットには以下のようなものがあります。
- キャリアアップにつながる
- モチベーションや満足度が上がる
- 人事評価が公平になる
それぞれについて下記で解説します。
キャリアアップにつながる
タレントマネジメントは従業員一人ひとりの能力や個性を一元管理します。
そのため、従業員自身が自分の強みや不足している能力を把握しやすくなります。
自分の強みや不足部分を把握すると、自ずと「強みを伸ばしたい」「不足部分をカバーしたい」と考えるようになります。
その結果、従業員の自発的なキャリア形成を促し、キャリアアップにつながることが期待できます。
モチベーションや満足度が上がる
タレントマネジメントで適材適所の人員配置を行うと、従業員は自分の能力や個性に合ったポジションに就くことができます。
適した配置で業務を行うとパフォーマンスを発揮しやすくなります。
その結果、モチベーションや満足度が高まり、パフォーマンスが向上するといった好循環が生まれます。
人事評価が公平になる
人事評価に公平性や客観性を持たせるためには事実に基づいたデータで評価することが重要です。
タレントマネジメントは従業員の能力や個性を可視化し、一元管理するため、人事評価を公平に行うことができます。
タレントマネジメントの導入フロー
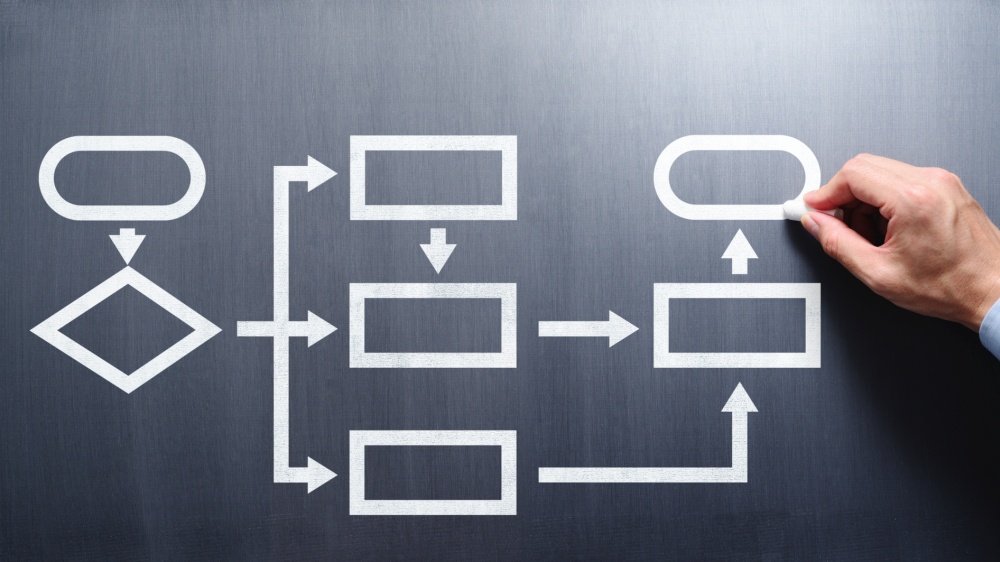
タレントマネジメントの導入フローは以下のとおりです。
- 現状を把握する
- 課題を洗い出す
- 目標とゴールの設定
- 人材情報の収集・整理
- 人材(タレント)の育成計画と採用計画の作成
- 人材(タレント)の新規採用、人材開発
- 人材の配置
- モニタリング・評価
- PDCAを回す
それぞれ順を追って解説します。
現状を把握する
まずは自社の人材管理の現状を把握します。
具体的には以下のような項目を数値化し、データベース化します。
- 従業員の人数
- スキル
- 目標
- 現時点の評価 など
こうすることで、そのようなスキルを持った人材がどの程度いるのか把握でき、不足している部を見出すことにつながります。
新たな人材を採用する際も何に着目すべきかが明確になります。
課題を洗い出す
自社の現状を把握したら、課題を洗い出します。
このとき、採用・人事部門の課題や従業員一人ひとりの課題だけでなく、経営戦略の実現と継続的な成長を見据えた課題まで踏まえて考えます。
経営戦略や中長期的な目標については、人事・採用部門だけでなく、経営層も含めて議論するようにしましょう。
目標とゴールの設定
前ステップで洗い出した課題を基に目標とゴールを設定します。
タレントマネジメントはあくまで目標を達成するための手段にすぎません。
人材をデータベース化しただけで活用しなければ何の意味もありません。
また、タレントマネジメントは導入後のモニタリングと評価が非常に重要になります。
達成度を見るためにも目標・ゴールを設定する際は「どの従業員に」「いつ」「どのようなタイミングで」「何を」「どのようにするのか」まで定量的に定めましょう。
人材情報の収集・整理
課題を洗い出し、目標・ゴールを設定したら、自社の人材情報を収集し、整理してデータベース化します。
データベース上で管理する項目には以下のようなものがあります。
- 人材基本情報:氏名、年齢、性別、所属、在職年数、家族構成 など
- 資格・能力:保有資格・技術、能力、スキル、など
- 経歴・実績:業務実績、キャリア、表彰実績 など
- 勤怠情報:勤務態度、休暇取得状況、残業や休日出勤の状況 など
- 志向性・価値観:従業員の志向性、価値観、考え方など
従業員一人ひとりの情報をデータベース化することで、どのような人材が在籍しているのか、どのような人材が足りていないのかがすぐにわかるようになります。
人材(タレント)の育成計画と採用計画の作成
の育成計画と採用計画の作成.jpg)
レントマネジメントのゴールと現状にギャップがある場合は、それを埋めるための施策を検討します。
ギャップを埋めるための施策としては大きくわけて育成と採用の2つがあります。
ギャップを埋めるための人材を採用するとなると時間もコストもかかります。
そのため、まずは社内の人材を育成して対応するほうが望ましいと言えます。
社内の人材を育成する手法については以下の2つがあります。
- 現状の従業員の成長を促す
- 異動させて育成する
いずれの場合も資格取得や研修受講などの費用と時間がかかるため、それらを計画に盛り込みます。
社内の人材を育成する手法は新しい人材を採用するよりはコストを抑えられます。
しかし、「動かせる人材がいない」「適切な人材がいない」という場合は新しい人材を採用することになります。
この場合も、採用基準や要件、費用、いつまでに採用するのかなどを細かく決め、計画に盛り込みます。
なお、人材要件や必要人数は現場によって異なります。現場と連携を取りながら設定しましょう。
人材(タレント)の新規採用、人材開発
既存人材を育成する場合、育成計画に基づいて育成を行います。主な人材育成方法は以下の2つがあります。
- OJT(On-the-Job Training):実際の業務を経験するなかで指導を受け、業務を身に着ける
- OFF-JT(Off-Job Training) 社内外研修やセミナー、eラーニング、通信教育などで育成する
このほか、コーチングやメンタリング、プロジェクトや部署のローテーションといった方法もあります。
新たに人材を採用する場合は採用計画に基づいて採用活動を行います。
人材の配置
人材を発掘(採用または育成)したら、データベースを整理し、発掘した人材を最適なポジションに配置します。
モニタリング・評価
人材を配置したら、定期的にモニタリング、評価を行います。
この場面は現場の責任者とタレントマネジメント担当者の連携が非常に重要になります。
モニタリングする際は設定した目標に対する進捗状況を確認し、従業員の状態の変化を把握します。
進捗状況によってフォローアップや調整を行い、計画が適切でないと判断した場合は育成計画の見直しも併せて行います。
例えば、OJTでは不十分だという場合はeラーニングや外部講習の受講などを追加するなどがあります。
どうしてもギャップが埋められそうにない場合は本人と面談を行い、人材の再配置も検討します。
適切でない配置を続けると生産性低下や離職につながる恐れがあります。
モニタリングを行ったら、現場の上司や責任者が公平に評価を行い、本人にフィードバックします。
このとき、評価結果や進捗、本人の意向も含めて人事部門に共有しましょう。
なお、評価結果に応じて報酬制度も整備すると良いでしょう。こうすることで、人材のモチベーションアップにもつながります。
PDCAを回す
タレントマネジメントは一回の運用で最適化できるものではありません。
仮説と検証を繰り返し、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。
こうすることで、タレントマネジメントの計画や運用がブラッシュアップされ、分析精度の向上につながります。
タレントマネジメントシステムとは

タレントマネジメントは経営層や現場など部署間での連携が重要です。
従業員数が多くなると、導入から運用までに膨大な時間を要してしまいます。
近年、タレントマネジメントの導入を支援するためのシステムが各社からリリースされています。
タレントマネジメントシステムの機能
タレントマネジメントシステムは各社様々なものがリリースされていますが、主な機能には以下のようなものがあります。
- 人材情報管理:従業員のプロフィールや能力のデータベース化、検索機能。
- 育成計画の管理:人材育成の計画立案、進捗管理機能。
- 後継管理:リーダーなどの特定のポジションの不足や重複、候補者選出、育成管理機能。
- 目標管理:従業員一人ひとりに適した目標管理、マネジメントの一元管理。
タレントマネジメントシステムの選び方
タレントマネジメントシステムを導入する際は以下のポイントを踏まえて選びましょう。
- 課題解決につながるか
- 利便性
- サポート体制
- 費用対効果 など
タレントマネジメントシステムを導入すればすべてが解決するわけではありません。
選択するツールによって、できること、得意とすることが違います。
企業規模や業種によっても適切なツールが異なります。また、誰が担当するのかによっても選択すべきツールが変わります。
システムを導入した結果、担当者の工数が増えてしまったり、うまく使いこなせず無駄になってしまったりするケースもあります。
特に外部システムを導入する際は数十万から数百万の費用がかかることもあります。
システムを導入する際は必ず見積りを取り、費用対効果も考えて慎重に判断しましょう。
タレントマネジメントを成功に導くポイント

タレントマネジメントを成功に導くポイントには以下のようなものがあります。
- 目的を明確にする
- 手段が目的にならないよう注意する
- 人材情報の管理を徹底する
- 中長期的な視点で運用する
- 継続的にプロセスの見直しを行う
- 組織全体への周知徹底・協力要請
- バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを併用する
それぞれについて下記で解説します。
目的を明確にする
タレントマネジメントを効率的に運用するためには目的を明確にし、常に意識することが重要です。
目的を明確にしたら組織全体に共有します。
このとき、経営戦略の実現や継続的な成長などの最終目標だけでなく、人材育成や人員配置などの具体的な目標まで共有します。
目的を共有する際は経営層から現場まで明確に伝えることが重要です。
手段が目的にならないよう注意する
タレントマネジメントの最大の目的は経営戦略の実現と継続的な成長です。
また、タレントマネジメントの導入後もモニタリングや評価、定期的な見直しなどが必要です。
タレントマネジメントを行うこと自体が目的ではないことを理解して取り組みましょう。
人材情報の管理を徹底する
タレントマネジメントは人材情報の正確性が重要です。
情報が古いままだと適切なマネジメントができなくなります。
タレントマネジメントで扱うデータは定期的に更新し、最新の状態を保ちましょう。
人材情報を最新の状態に保つためのポイントは以下となります。
- ひとつのシステムで一元管理を行う
- 個人情報の取り扱いに注意する
- セキュリティ対策を徹底する
- デジタルツールなどを活用し、情報をリアルタイムで管理する など
人材情報の管理を行う際は、管理項目を厳選することも重要です。
データ量が増えすぎると情報の見落としが生じる恐れがあります。
人材情報を管理する際は必要な情報を厳選し、集中的に管理すると良いでしょう。
中長期的な視点で運用する
タレントマネジメントシステムはすぐに効果が出るものではありません。
中長期的(3年~10年)な視点で運用・管理することが重要です。
中長期的な視点を持たずにタレントマネジメントを導入すると、十分な効果が得られなくなるばかりか、生産性の低下や従業員の離職を招く恐れがあります。
継続的にプロセスの見直しを行う

タレントマネジメントは中長期的な運用になります。
その間、従業員の情報やデータが集約されるため、長期間管理し続ける必要があります。
管理する情報が増えると、担当者の負担が増え、処理が追い付かなくなる可能性があります。
タレントマネジメントを導入する際はリソースの確保し、業務プロセスの見直しを適宜行うことが重要です。
組織全体への周知徹底・協力要請
タレントマネジメントは自動的に行われるものではなく、現場の協力がなければ成り立ちません。
人材情報を集め、最新のものに更新したり、採用・育成を行うためには組織全体の協力が必要です。
タレントマネジメントに限らず、新しい仕組みを導入する際は担当者や現場に一定の負担がかかります。
制度導入の目的を社内全体に周知し、理解してもらったうえで協力を要請します。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを併用する
既存の従業員を活用する場合はこれまでの情報を収集し、データを蓄積することが可能です。
一方、人材を新しく採用する場合、人材情報が社内にありません。面接や提出書類から得られる情報も限られています。
また、面接と書類だけで候補者自身が主張する情報が適切かどうかを判断できません。
このような場合、採用前にバックグラウンドチェックやリファレンスチェックを導入することをおすすめします。
バックグラウンドチェックは候補者の主張する内容に虚偽がないかを確認するものです。
一方、リファレンスチェックは候補者の前職の職場にヒアリングを行い、働きぶりや実績を確認するものです。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを活用することで、自社に最適な人材かどうかを見極める判断材料のひとつになります。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックで収集した情報をデータベースに登録すれば、適切な育成や人員配置に役立てることができます。
まとめ
タレントマネジメントは経営戦略実現と組織の継続的な成長を目的とした取り組みです。
すぐに結果が出るものではなく、中長期的な視点で行う必要があります。
成功に導くためには、経営層から現場まで組織が一体となって取り組むことが重要です。
また、タレントマネジメントシステムは人材情報の管理・更新、定期的なモニタリングや評価、プロセスの見直しなどが必要になります。
管理する人材情報を厳選したり、外部ツールを活用したりするなど、効率的に取り組むと良いでしょう。
新たに人材を採用する際は、バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを活用し、候補者を見極めることも重要です。
得られた結果をデータベースに登録すれば、育成や人員配置の際も活用できます。
レキシルなら経験豊富な調査会社のクオリティをリーズナブルな価格でご提供いたします。
タレントマネジメントを導入する際はぜひご活用ください。
※1 厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」

