採用のスクリーニングとは?導入の流れと手法、メリット・デメリット
2025.05.19

多くの応募者のなかから自社に適した人材を見つけ出すのは至難の業です。
採用を効率よく行うため、採用の初期段階で応募者を絞り込む作業がスクリーニングです。
しかし、スクリーニングの基準や手法を間違えると、適切に絞り込めないどころか、採用に手間も時間もかかってしまい、却って効率が悪くなる恐れがあります。
採用活動でスクリーニングを導入するのであれば、適切に行うことが重要です。
この記事を最後まで読むことで以下のことがわかります。
- 採用スクリーニングのメリット・デメリット
- 採用スクリーニングの代表的な手法
- 採用スクリーニングの流れ
- スクリーニングで採用を成功させるためのポイント
採用活動におけるスクリーニングとは
スクリーニングは英語で表記するとscreening、直訳すれば「ふるいわけ」になります。
スクリーニングは採用に限らず、様々な場面で用いられる言葉です。
採用活動におけるスクリーニングとは、応募者を最低限の基準に照らし合わせ、次の選考プロセスに進む人材を絞り込むことを言います。
スクリーニングなしで選考を進めてしまうと、応募者全員と面接を行うことになり、膨大な時間とコストがかかります。
事前にスクリーニングで基準を満たさない人材を除外すれば、後の選考プロセスでの時間とコストを削減できるようになります。
スクリーニング基準と採用基準の違い
スクリーニングは最低限の基準に適合しない人材をふるいわける(除外する)ものです。
スクリーニングは採用活動の序盤で行われます。
一般的な採用手法である書類選考もスクリーニングのひとつの手段です。
スクリーニング基準は面接など、次の採用段階に進むための基準です。
スクリーニング基準として有名なものに「学歴フィルター」があります。これは、面接に進むための基準としてある一定の学歴・偏差値を設定するものになります。
一方、採用基準は自社が求める人材を判断するための指標です。
スクリーニング基準を満たし、面接に進んだとしても、採用基準を満たしていないと判断されれば、採用にいたらないことがあります。
例えば、偏差値の高い大学を出ており、面接に進んだとしても、採用にいたらないというのは、スクリーニング基準と採用基準が異なることによるものです。
マッチングとの違い
「スクリーニング」と混合されがちな言葉に「マッチング」があります。
両者には大きく以下の違いがあります。
- スクリーニング:基準に適合しない人材を除外する
- マッチング:基準に適合する人材をピックアップする
また、スクリーニングは主に選考の初期段階で行われるのに対し、マッチングはスクリーニングが済んだ後の採用プロセスで行うといった違いがあります。
採用スクリーニングのメリット

スクリーニングを導入すると以下のようなメリットが期待できます。
- 採用したい人材の選考に時間をかけられるようになる
- 人材の即戦力化と定着率向上につながる
- 時間とコストの削減につながる
- 応募者の納得感が得られやすい
それぞれについ下記で解説します。
採用したい人材の選考に時間をかけられるようになる
応募者全員に対して面接を行うとなると、一人あたりにかけられる時間が短くなります。
一方、採用スクリーニングを導入すれば、初期段階で自社に合わない人材を除外できるため、採用したい人材の選考だけに時間をかけられるようになります。
その結果、採用効率や面接の精度が上がり、採用ミスマッチを防ぐことにつながります。
人材の即戦力化と定着率向上につながる
採用面接の精度が上がれば、真に自社に適した人材を採用することができ、入社後の即戦力化も期待できます。
即戦力でない場合であっても、人材をどのように育成をすれば良いかが明確なため、育成コストを抑えることにつながります。
応募者にとっても自分のスキルや特性に合った企業に入社できるため、能力を発揮しやすくなり、エンゲージメントや定着率向上につながります。
活躍人材が長く定着すれば、かけた採用・育成コストが無駄になりません。
時間とコストの削減につながる
応募者のなかには、採用基準との乖離が大きい人材もいるかもしれません。
このような人材を事前に除外すれば、ある程度自社の基準に適した人材だけを選考することができます。
人材を厳選して選考するため、面接の回数や時間、担当者の負担軽減につながります。
もちろん、スクリーニング自体にも時間とコストがかかります。
しかし、スクリーニングを行えば面接に割かれる時間や工数を軽減でき、ミスマッチを防いだり、即戦力化・定着率向上につながるという大きなメリットが得られます。
スクリーニングのコストや時間を抑えたいという場合は、スクリーニングの目的や応募者数、導入コストのバランスを見て、どの手法を用いるか慎重に検討しましょう。
応募者の納得感が得られやすい
面接時間が短く、コミュニケーションが十分でない場合、合否結果に対して「最初から不合格にするつもりだったのでは」「不誠実だ」という印象を応募者に持たれる恐れがあります。
一方、スクリーニングを行うことで、応募者一人ひとりの選考に十分な時間を割くことができれば、充実した面接を実施できます。
こうすることで、採用者・不採用者いずれにとっても、合否に対する納得感が得られやすくなります。
採用スクリーニングのデメリット

採用スクリーニングの導入には以下のデメリットがあります。
- 採用担当者の主観が入りやすい
- 自社に適した人材を見逃す可能性がある
- 人材の多様性が失われる恐れがある
- 応募者に不信感を与える可能性がある
それぞれについて下記で解説します。
採用担当者の主観が入りやすい
スクリーニング基準を設定する際、担当者の主観が入る恐れがあります。
担当者の主観や先入観が入り込みすぎると、適切なスクリーニングができなくなる恐れがあります。
スクリーニング基準はできるだけ採用担当者の主観や先入観が入り込まないよう、客観的な視点で検討することが重要です。
自社に適した人材を見逃す可能性がある
スクリーニング基準に基づいてふるいわけを行うだけでは、自社にマッチする人材も除外される恐れがあります。
スクリーニングに用いる情報は限られており、すべての要素を評価するわけではありません。
スクリーニングで除外された人材であっても、面接に進めば優れたスキルや才能を見出すことができたかもしれません。
スクリーニングは真に優秀な人材を逃す恐れがあるということを理解しておきましょう。
人材の多様性が失われる恐れがある
スクリーニングではあらかじめ設定した基準をベースに採否を判断します。
そのため、同じような人材だけが選考に残り、組織に新しい風を入れ込む人材を取り残す可能性があります。
結果的に人材の多様性が失われ、イノベーションが起きにくく、社会のニーズに対応できない組織になってしまう恐れがあります。
応募者に不信感を与える可能性がある
スクリーニングの段階で不採用となると、「公平に評価されていない」などと応募者が感じる恐れがあります。
面接前に予告されていない試験が行われたり、書類段階で不採用になると「〇〇だから落とした」「最初から採る気がなかった」と思われる可能性もあります。
最悪の場合、応募者が企業について悪い口コミを拡散し、企業の評判や信用が低下する恐れもあります。
採用スクリーニングの代表的な手法

採用スクリーニングの代表的な手法には以下のようなものがあります。
- 履歴書(エントリーシート)・職務経歴書
- 適性検査
- 転職エージェントの活用・ダイレクトリクルーティング
- スキルテストやオンライン試験の実施
- 採用管理システム
- 動画面接
- AIによる応募者評価
- バックグラウンドチェック
- リファレンスチェック
それぞれについて下記で解説します。
履歴書(エントリーシート)・職務経歴書
履歴書(エントリーシート)や職務経歴書は、以前より多くの企業が採用しているスクリーニング手法です。
応募時に書類の提出を求め、記載内容によって次の選考プロセスに進めるかどうかを判断します。
応募書類には応募者の学歴や職歴、経験、保有資格のほか、文章作成能力や文章の構成から人柄を見出すこともできます。
適性検査
適性検査の実施も代表的なスクリーニング手法のひとつです。
応募者の能力や人柄が企業や職務にマッチしているかを評価するものです。
性格適性と基礎学力の件さ、心理検査などが有名です。
適性検査の代表的なものとしてSPIやクレペリンテストなどがあります。
転職エージェントの活用・ダイレクトリクルーティング
転職エージェントの活用やダイレクトリクルーティングもスクリーニング手法のひとつです。
ダイレクトリクルーティングとは、自社で設定したスクリーニング基準に従い、求職者にアプローチするものです。
候補者から応募がある前に、自社でスクリーニングをかけ、候補者を絞り込んだうえでアプローチします。
転職エージェントを活用している場合は、スクリーニング段階からサポートしてもらう方法もあります。
転職エージェントであれば自社の採用担当者の主観が入らないため、公平なスクリーニングが可能です。
スクリーニングを外注するため、採用担当者の負担を軽減することにもつながります。
採用管理システム

採用管理システムとは、求人・選考・面接・採用といった採用活動に関わる業務を一元管理するシステムです。
すべてのプロセスが集約されるため、効率よく採用活動を進めることができます。
システムによっては自社で設定したスクリーニング基準によって、スクリーニングする機能を持つものもあります。
採用管理システムは大きくオンプレミス型とクラウド型にわかれます。
オンプレミスとはITシステムやソフトウェアを自社の施設内で運用する形態を言います。
システムを自由にカスタマイズできるなど、柔軟性が高く、セキュリティ対策を万全にできるといったメリットがあります。
一方、システム管理に専門知識が必要なこと、トラブルの際に担当者の負担が増えること、サーバー設置や運用コストがかかるといったデメリットもあります。
クラウド型はオンライン上のサーバーにある既成のシステムを利用する形態です。
ネット環境があればどこでも使える、特別な知識がなくても使える、トラブル対応をクラウド提供元に任せられる、イニシャルコストを抑えることができるといったメリットがあります。
一方、既成システムのため、欲しい機能が備わっていないケースがあり、セキュリティ対策は提供元次第になるといったデメリットもあります。
動画面接
動画面接とは、履歴書やエントリーシートを動画にしたものです。
履歴書や職務経歴書に記載した内容について、文章ではなく、動画を通して、自分の言葉で伝える手法です。
動画面接を活用することで、書類に記載された内容のほか、応募者の印象や言葉遣いなどもチェックできます。
募集職種が営業職や接客業など、第一印象についてもスクリーニングしたいという場合に適した手法です。
AIによる応募者評価
近年はAIによるスクリーニングが注目されています。
AIによるスクリーニングには以下のようなものがあります。
- 応募書類や適性検査の結果をまとめて数値化する
- 採用データやアルゴリズム、キーワードマッチングなどから基準を満たす応募者のみを抽出する
- 応募者の応募書類をスキャンし、スキルセットや経歴を他の候補者と評価する
- 過去の実績から、どれだけ自社で貢献できるかを予測する
いずれも、自社で判断基準を設定すれば、あとはAIがスクリーニングするため、採用担当者の主観が入らず公平な評価が期待できます。
バックグラウンドチェック
バックグラウンドチェックも近年注目されているスクリーニング手法のひとつです。
バックグラウンドチェックとは、企業が調査期間に依頼し、応募者の主張する経歴や実績に虚偽がないか、また、破産歴や犯罪歴、SNSでの言動などを調査するものです。
応募書類に記載された内容や主張する内容は応募者の自己申告によるものです。
バックグラウンドチェックは、問題となりうる人材を除外する目的で行うケースが多いようです。
なお、米国の人事コミュニティHR.comの2021年に発行されたレポートによると、アメリカでは企業の95%がバックグラウンドチェックを実施しているそうです。
参考:HR.com「Background Screening:
Trends in the U.S. and Abroad
(https://pubs.thepbsa.org/pub.cfm?id=FB36B937-C9D5-A941-7720-4047386F38B0)」 ※1
リファレンスチェック
リファレンスチェックは主に中途採用のスクリーニングの際に注目されている手法です。
リファレンスチェックとは、企業が専門調査期間に依頼し、応募者の前職の関係者に応募者の人柄や勤怠、勤務態度などについて問い合わせを行うものです。
バックグラウンドチェックと同様に、入社後にトラブルを起こしかねない人材をふるいにかける目的で実施するケースが多いです。
採用スクリーニングの流れ

採用スクリーニングの流れは以下となります。
- 採用スクリーニング基準の設定
- スクリーニング方法の選定
- スクリーニングプロセスを構築する
それぞれについて順を追って解説します。
採用スクリーニング基準の設定
採用スクリーニングはスクリーニング基準の設定が重要です。
前述のとおり、スクリーニングは最低限の基準に適合しない人材をふるいわけるものです
まずは自社が求める人材を設定し、採用基準を決めたうえで、最低限満たすべき基準をスクリーニング基準として反映させます。
一般的には以下の項目について設定することが多いです。
- 学歴
- 職務経歴
- 経験
- 資格
- スキル
- 職務適性
- 性格
- 価値観・志向性・考え方 など
どの項目を選択するかについては企業や募集職種、ポジションによって異なります。
項目を選んだら優先度をつけていきます。このとき、必須項目は何で、どこまでクリアすべきかまで決めておきます。
スクリーニング方法の選定
次にスクリーニング方法を選定します。
前述のとおり、スクリーニング方法には様々なものがあり、それぞれスクリーニングできる内容や目的が異なります。
スクリーニング項目のうち、どの項目を重視するのか、いくらまでコストをかけられるかによって選択する手法が変わります。
ミスマッチを防ぎ、採用精度を上げたいのであれば、複数の手法を組み合わせても良いでしょう。
履歴書(エントリーシート)や職務経歴書でスクリーニングする企業が多いですが、これらの情報はあくまで応募者の自己申告によるものです。
履歴書・職務経歴書とバックグラウンドチェックやリファレンスチェックを組み合わせて情報の正確性を確保したうえで、他の手法を組み合わせると採用精度の向上につながります。
スクリーニングプロセスを構築する
スクリーニング基準を設定し、手法を選択したら、スクリーニングプロセスを構築します。
プロセスを構築できたら、手順に沿ってスクリーニングを行います。
応募者をスクリーニングする際は5段階評価で点数をつけ、何点以下だと除外などと評価基準を決めておくと良いでしょう。
こうすることで、面接に進んだ際も、「どの応募者について、どの視点で評価すべきか」がわかりやすくなります。
スクリーニングで採用を成功させるためのポイント

スクリーニングを導入して採用を成功させるためには以下のポイントを押さえておきましょう。
- 採用基準とスクリーニングの基準を明確に区別する
- 社内の優秀人材の特性を考慮する
- スクリーニングの種類と特性を理解する
- 情報を過信しない
- バイアスを排除する
- 複数の手法を組み合わせる
- 多様性を確保する
- 応募者の良い部分も見るように心がける
- プライバシーの保護に努める
- PDCAを回す
それぞれについて下記で解説します。
採用基準とスクリーニングの基準を明確に区別する
ここまで説明したように、採用基準とスクリーニング基準は異なるものです。
スクリーニング基準は基準に満たない人材をふるいわけるもの、採用基準は自社に適した人材かどうかを判断するものです。
スクリーニング基準を採用基準と同レベルに厳しくすれば、応募者が集まらなくなる可能性もあります。
一方、採用基準をスクリーニングと同レベルに緩めれば、採用スクリーニング自体が意味を成さなくなったり、計画通りに採用を進められなくなったりする恐れがあります。
それぞれの基準を明確に区別し、適切に設定しましょう。
社内の優秀人材の特性を考慮する
適性や人柄をスクリーニング基準に入れる際は、「誠実」「活発」などの曖昧な言葉で定義すると、スクリーニングの効果が得にくくなります。
このような場合、社内で活躍している人材の人柄を具体的に言語化し、基準に含めると良いでしょう。
具体例を下記に挙げます。
- 話すときや話を聞くときに相手の目を見る
- 相手の話を遮らず、寄り添う言葉をかけるなど、傾聴・共感の姿勢が見てとれる など
人柄を見抜く方法や質問例としては下記の記事もご覧ください。
参考≫≫
人柄重視採用とは?メリット・デメリットと人柄を見極めるポイント
スクリーニングの種類と特性を理解する
スクリーニングを適切に行うためには、各スクリーニング手法の種類と特性を理解しておく必要があります。
自社のスクリーニング基準のうち、どの項目を重視するか優先順位をつけることで、適切なスクリーニング手法が見つかりやすくなります。
情報を過信しない
採用基準とスクリーニング基準は内容も目的も異なります。
スクリーニングの評価が高かったからといって、採用基準もクリアするとは限りません。
スクリーニングの情報を過信することなく、面接や他の採用手法で採用基準を満たしているのか、自社に適した人材かどうかを慎重に見極めるようにしましょう。
バイアスを排除する
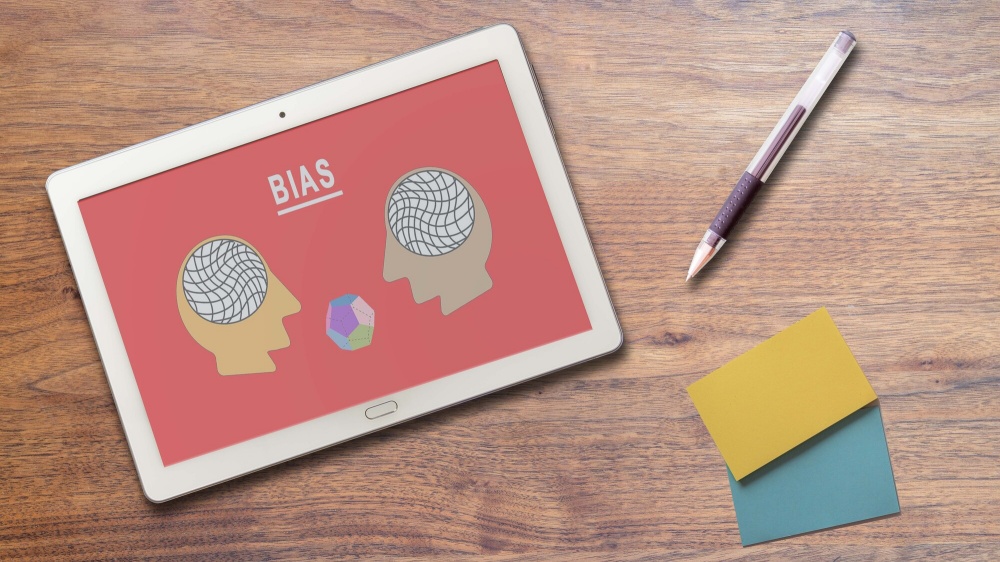
人間がスクリーニングを行うと、担当者の主観や先入観などのバイアスが入り込む可能性があります。
スクリーニング効果を高めるためにも、できるだけバイアスによる影響を減らす工夫が不調です。
バイアスを減らすための手法の例には以下のようなものがあります。
- 複数人で評価する
- 複数の項目で複合的に評価する
- AIツールを活用する など
複数の手法を組み合わせる
スクリーニングを行うと自社に適した人材を見逃す恐れがあります。
自社の成長に貢献できる人材を見逃さないためにも、複数のスクリーニング手法を組み合わせ、総合的に判断することが重要です。
複数の手法を組み合わせることで、優秀な人材を見逃しにくくなるだけではなく、スクリーニングの質も上がるため、除外したい人材を見抜くことにもつながります。
多様性を確保する
組織に異なる視点を持つ人材を採用することと、新しい風が入り込み、イノベーションが起きやすくなります。
そのため、スクリーニングの際は人材の多様性を確保することも重要です。
同じような人材に偏らないよう、多様なスキルや背景を持つ人材を取り入れられるようにスクリーニングすることが重要です。
応募者の良い部分も見るように心がける
スクリーニングは応募者をふるいわけるものです。そのため、「〇〇を満たしていない」といった減点評価になってしまいます。
また、スクリーニングは採用効率を上げるものであって、万能なものではありません。
スクリーニングで選ばれなかった応募者やスクリーニングで低評価だった応募者のなかには、自社で活躍できるポテンシャルを持つ人材がいるかもしれません。
マイナスの側面だけでなく、良い部分も見るなど、バランスの取れた評価を心がけることをおすすめします。
具体的には以下のような方法があります。
- 面接に進んだ応募者についてはできるだけ良い部分を見るようにする
- スクリーニング基準を満たしていないが「〇〇の点を評価して面接に進める」と面接官に伝えて、面接に進める など
プライバシーの保護に努める

採用スクリーニングでは、応募者のプライバシー保護を徹底しましょう。
スクリーニングの際に入手した情報は適切に管理し、第三者の手に渡らないようにすることが重要です。
具体的には以下のような方法があります。
- 応募者の個人情報の保管場所を関係者以外が閲覧できないようにする
- 応募者の個人情報を閲覧できる媒体を限定する
- 個人情報の入った媒体を持ち出しできないようにする など
同じ社内であっても、応募者の同意なしに無関係の部署に情報を回すことも避けましょう。
自分の知らないところで個人情報が漏れたことを応募者が知れば、企業に対して不信感を抱くことにつながります。
個人情報の流出や不正利用についての対策を講じ、取扱いには細心の注意を払いましょう。
PDCAを回す
スクリーニングを行ったら、結果を分析し、課題や問題点を抽出します。
問題や課題を抽出したら、スクリーニング基準や採用プロセスの見直しを行い、PDCAを回していきましょう。
このとき、人事・採用担当だけでは課題が見つからないこともあります。
実際の現場担当者にヒアリングをするなど、様々な視点を交えて評価することが重要です。
まとめ
採用におけるスクリーニングについて解説しました。
採用スクリーニングを行うことで、採用効率が上がり、自社に適した人材の採用につながります。
しかし、スクリーニング手法や基準の設定が適切でない場合、優秀な人材を見逃したり、人材の多様性を失う恐れもあります。
ここで解説した内容を参考に、スクリーニング基準を適切に設定し、自社に合ったスクリーニング手法を選択しましょう。
また、自社で活躍できる人材を見逃さないためにも、複数の手法を組み合わせ、総合的に判断することも大切です。
ほとんどの企業で、履歴書(エントリーシート)や職務経歴書を使ったスクリーニングが採用されていますが、これらは応募者本人の自己申告によるものです。
応募書類や本人の主張するスキルや経験に虚偽があれば、スクリーニングの意味がなくなってしまいます。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックと他のスクリーニング手法を組み合わせることで採用精度を高め、自社に適した人材の採用を行いましょう。
※1 HR.com「Background Screening:Trends in the U.S. and Abroad」

