エンパワーメントとは?社員の主体性を引き出し、生産性を上げる方法
2025.06.30

エンパワーメントとは、従業員の潜在能力や特性を引き出し、自己実現や成長を促すことにより、組織力を高めていく方法です。
労働力不足や目まぐるしく変化するビジネス環境において、エンパワーメントに注目が集まっています。
この記事を最後まで読むことでいかのことがわかります。
- エンパワーメントの意味
- エンパワーメントが注目された背景
- エンパワーメントのメリット・失敗例
- エンパワーメントの導入準備・導入手順
- エンパワーメントを成功させるポイント
ビジネス・人事領域におけるエンパワーメントの意味
エンパワーメントとは、従業員のスキルや意欲を引き出し、成長や自己実現を促すものを言います。
エンパワーメント(empowerment)とは、「力を与える」という意味の「empower」の名詞形です。
ビジネス領域におけるエンパワーメントは「権限委譲」という意味で用いられ、エンパワメントと呼ばれることもあります。
一般的には管理者が持つ権限を従業員に移譲し、従業員の裁量を広げることで、従業員が主体的かつ柔軟に行動し、個々の能力を引き出すことで組織全体のパフォーマンスを向上し、目標達成に向かうことを言います。
エンパワーメントが注目された背景
エンパワーメントが注目されるようになった背景には以下のようなものがあります。
- VUCA時代における人材の育成
- 次世代リーダー育成の必要性
- 中途人材の活用の必要性
それぞれ、下記で解説します。
VUCA時代における人材の育成
エンパワーメントが注目されるようになった背景のひとつにVUCA時代の到来があります。
VUCAとは目まぐるしく変化し、予測不能な時代の特徴を表す言葉です。
元々米軍内で使われてきた用語で、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の4つの単語の頭文字を取った造語です。
テクノロジーの進化や社会情勢が目まぐるしく変化するなか、ビジネス環境は不確実性が高まり、未来予測が難しくなっています。
このような状況のなか、環境の変化に柔軟に対応し、新たな価値を生み出すことが多くの企業に求められています。
VUCA時代では、従来のトップダウン型の組織運営では意思決定に時間がかかり、機会損失が生じる恐れがあります
迅速に意思決定を進めるためにも、現場に判断を委譲し、機会損失を防ぐことが重要なのです。
次世代リーダー育成の必要性

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、多くの企業で人材不足が問題になっています。
事業活動を継続するためにも、限られた人材のなかから次世代を担うリーダーを育成し、経験を積ませることが重要です。
そのため、若いうちから責任を伴う権限を従業員に与え、リーダーシップや責任感を養わせていく必要があるのです。
中途人材の活用の必要性
エンパワーメントは中途採用の活用においても効果を発揮します。
近年、転職が珍しいことではなくなり、人材流出も激しくなっています。
入社後早い段階で中途人材に権限を与えることで、組織に馴染みやすくなり、能力を存分に発揮しやすくなります。
分野別のエンパワーメントの意味
エンパワーメントは分野や領域によって目的や意味合いが変わります。
ここでは、ビジネス・人事領域以外の下記の3つの分野について、エンパワーメントの意味を解説します。
- 教育分野
- 介護・看護分野
- 福祉分野
それぞれについて下記で解説します。
教育分野
教育分野におけるエンパワーメントには「誰しもが持つ潜在能力や価値を引き出し、自分自身で人生を切り開いていくために必要なスキルや自信を身に着けられるよう支援する」という意味があります。
児童生徒が主体性や自信を持ち、夢に向かって目の前の課題や困難に立ち向かい、解決するために自ら行動することがVUCA時代を生き抜くために必要な教育の在り方なのです。
介護・看護分野
介護や看護分野におけるエンパワーメントとは「患者やサービスを受ける側がただ受け身になるのではなく、自分自身で決断させ、そのプロセスに主体的に関与すること」という意味があります。
看護や介護の現場では、どうしても患者側が「治療(サービス)を受ける」という立場になってしまいます。
また、「せっかくやってもらっているのにわがままを言うことはできない」として、患者が自分の意見を伝えにくいという現状があります。
しかし、治療やサービスの効果を引き出すためには本人の前向きな姿勢や努力が不可欠です。
そのため、患者やサービスを受ける人が自分でできることを増やし、「ひとりでできる」という自信を与えられる環境を整えることが大切になります。
福祉分野
福祉分野におけるエンパワーメントとは「受益者が本来持っている能力や権限を最大限に発揮できるような条件整備を行うこと」という意味があります。
これまでは、国が受益者に対して一方的に支援をするという形が採用されていました。
しかし、これは受益者の自立を妨げるだけでなく、自由や裁量を奪うことにもつながってしまいます。
このような状況を改善すべく、福祉分野においてもエンパワーメントが重要だと考えられるようになりました。
エンパワーメントのメリット

エンパワーメントのメリットには以下のようなものがあります。
- 意思決定が迅速化することで業務効率が上がる
- 従業員の主体性が向上する
- 成功体験が蓄積されることでモチベーションが向上する
- マネジメント能力を習得できる
- 組織の生産性や競争力がアップし、顧客満足度が向上する
それぞれについて下記で解説します。
意思決定が迅速化することで業務効率が上がる
エンパワーメントは従業員に権限を委譲することになります。
これにより、意思決定が迅速になり、業務効率が上がり、生産性向上につながります。
従業員の主体性が向上する
権限を委譲することで、従業員の主体性や責任感の向上が期待できます。
上からの指示通りに動くだけは、主体性や責任感を育むことは難しいものです。
エンパワーメントにより、自分の裁量の範囲について自分で判断するようになれば、主体性や責任感の育成につながります。
成功体験が蓄積されることでモチベーションが向上する
エンパワーメントは従業員のモチベーション向上にも効果的です。
従業員が自ら考えて行動することで、自分の能力を最大限に発揮でき、自己実現がしやすくなります。
これにより、課題を解決したり、目標を達成するといった成功体験が蓄積されれば、仕事に対するモチベーションも高まります。
マネジメント能力を習得できる
エンパワーメントは従業員のマネジメントスキルやリーダーシップを引き出す効果があります。
従業員が裁量権を得ることで、自身が所属するチームのリーダー的な立場になり、チームをまとめる能力や状況を分析して課題解決に導く力が磨かれます。
この経験を重ねるうちに、従業員の潜在能力が発掘され、次世代のリーダー候補を見出し、育成できるようになります。
組織の生産性や競争力がアップし、顧客満足度が向上する
従業員が裁量権を持つことで、顧客や取引先に対しても柔軟でスピーディな対応ができるため、顧客満足度の向上につながります。
例えば、クレームが来たときやトラブルが起きたときに、現場の判断で迅速かつ適切に対応できれば、顧客離れを防ぎ、リピーター獲得にもつながります。
エンパワーメントの失敗例

エンパワーメントのよくある失敗には以下のような例があります。
- 適性のない従業員に権限委譲してしまい、損失が発生する
- 権限移譲ではなく責任放棄になる
- 権限移譲という手段が目的化する
- 個人の力が強くなり、まとまらなくなる
それぞれについて下記で解説します。
適性のない従業員に権限委譲してしまい、損失が発生する
従業員のなかには権限移譲に向かない人材もいます。
言われたとおりに動くことが染み付いており、自分で考えて行動するということができない人もいるのです。
また、そもそも権限を担う能力を有していない人材もいます。このような人材は上司からの指示通り動いたほうが能力を発揮できる場合があります。
さらに、権限を与えられることでモチベーションが上がる人がいる一方、プレッシャーを感じてしまう人もいます。
従業員の特性や希望を考慮しながら、その人材に適した範囲や重さで権限移譲することが重要です。
権限移譲ではなく責任放棄になる
権限移譲した段階では、従業員が責任まで果たせる立場にはありません。
そのため、従業員に権限を委譲した場合であっても、責任は上司が担保することになります。
これにより、従業員は自由に裁量を発揮できるようになります。
仮に、従業員が何らかの失敗や損失を出した場合は上司が責任を負う必要があります。
権限だけでなく、責任まで従業員に丸投げするのは、権限移譲ではなく、責任放棄です。
こうなると、従業員の不満が募り、モチベーションの低下や生産性の低下、離職者の増加につながる恐れがあります。
権限移譲という手段が目的化する
権限移譲の目的は「従業員の主体性を引き出し、成長を促すことで業務効率を上げること」です。
しかし、なかには「権限移譲を行う」という手段が目的になってしまい、権限移譲しただけで満足してしまうケースもあります。
エンパワーメントは部下に権限移譲をすることが目的ではありません。
本来の目的を見失わないように注意しましょう。
個人の力が強くなり、まとまらなくなる
エンパワーメントは従業員一人ひとりの主体性を引き出す効果があります。
しかし、個々の力が強くなりすぎると、協調性がなくなり、チームがまとまらなくなる恐れがあります。
組織の和が乱れると、生産性の低下や離職を招く可能性もあります。
エンパワーメントの導入準備

エンパワーメントを導入する際は事前準備が必要です。
事前準備の手順は以下となります。
- 経営層・管理職がエンパワーメントへの共通認識を持つ
- 従業員の能力開発
それぞれ順を追って解説します。
経営層・管理職がエンパワーメントへの共通認識を持つ
権限移譲について経営層や管理職が理解し、共通認識を持っていなければ、エンパワーメントは機能しません。
エンパワーメントを導入する前にまずは経営層や管理職をはじめ、全従業員が権限移譲の目的や内容を理解することが重要です。
例えば、経営層自らが経営方針を刷新し、従業員の挑戦や裁量を与えることを推奨する姿勢を示すと効果的です。
従業員の能力開発
権限を委譲しても、それを実践する能力が従業員に備わっていなければ意味がありません。
権限移譲をする従業員に対して、エンパワーメントを実践するためにはスキルや情報が必要であることを伝えたうえで、能力開発を行いましょう。
エンパワーメントの導入手順
事前準備が整ったら、エンパワーメントを導入します。
エンパワーメントの導入手順は以下のとおりです。
- エンパワーメントの宣言をする
- 目標とゴールの設定と理解を得る
- ルールの明確化と情報共有
- 権限移譲と支援・フォロー
それぞれ順を追って解説します。
エンパワーメントの宣言をする
まず全従業員に対し、企業の最高責任者や事業書のトップがエンパワーメントを推進することを宣言します。
単なる社内連絡ではなく、固い決意と熱意が伝わるように宣言することが重要です。
例えば、全従業員を一堂に集め、目の前で宣言するというのも良いでしょう。
このとき、従業員がエンパワーメントの必要性や流れについて理解できるように、わかりやすく伝えることも重要です。
具体的には下記の項目をわかりやすく説明すると理解が深まるでしょう。
- エンパワーメントが自社とって必要である理由
- 自社のどのような課題に有効なのか
- エンパワーメントはどのような手順で行うのか
- 従業員・会社にどのようなメリットがあるか
- 従業員一人ひとりに対してどのような影響があるのか など
目標とゴールの設定と理解を得る
エンパワーメントの宣言をしたら、目標とゴールを設定します。
このとき、通常よりやや難易度が高めの目標・ゴールを設定することが重要です。
こうすることで、従業員が権限を使いながら、課題を解決し、目標に達成するという体験を経験できるようになります。
なお、目標・ゴールを設定する際は全従業員の理解が得られている必要があります。
目標やゴールを設定したら、どのような理由で目標を設定したのかを説明しましょう。
一方、エンパワーメントや権限移譲と聞くと「面倒なことになる」と捉える従業員もいるかもしれません。
そのため、勉強会やディスカッションを開き、エンパワーメントに対する心配ごとや疑問を吐き出してもらいましょう。
従業員と向き合い、どのようなメリットがあるのかを丁寧に説明することで共感や理解を得られやすくなります。
エンパワーメントの導入で成功した企業事例などを説明すれば、従業員がエンパワーメント導入後のイメージがしやすくなり、理解を得やすくなるでしょう。
ルールの明確化と情報共有

権限移譲をする前にルールを明確に設定します。
権限の範囲外のことまで従業員が勝手に判断してしまうと、思わぬ損失が生じる恐れがあります。
具体的には以下のことを明確にし、社内に周知します。
- 権限を委譲する対象者の基準
- 対象者が意思決定できる範囲
- 対象者が遵守すべきこと など
権限だけ与えても、正しい意思決定はできません。
権限を委譲した従業員が適切な意思決定ができるように必要な情報を共有することも重要です。
このとき、組織の方向性から大きく外れないよう、経営戦略や企業方針、人事・経理状況などについても共有します。
なお、これらの情報は経営層など一部の人間しか知り得なかった情報も含まれます。
情報漏洩のリスクもあるため、情報を公開する範囲は「正社員かつ入社〇年経過している」など、明確に定めることが重要です。
限られた情報を共有されることは、その従業員を信用していることでもあるため、責任感も生まれやすくなります。
権限委譲と支援・フォロー
課題解決・目標を実現のために、従業員に権限を委譲し、意思決定と行動の自由を容認します。
権限移譲後はつい口を出したくなることもあるでしょう。
しかし、従業員を信頼して任せることにより部下の成長につながるのです。
一方、権限移譲後は思わぬトラブルが起きる恐れがあります。
上司や企業側が継続的に従業員をフォローする体制を整えておくことも重要です。
失敗したときは失敗を責めるのではなく、「失敗した理由は何か」「この失敗をどう生かすか」についてアドバイスを行いましょう。
エンパワーメントを成功させるポイント

エンパワーメントを成功させるポイントについてご紹介します。
- 権限を委譲する範囲を明確にする
- 判断基準を明確にする
- 報連相を徹底し、支援環境を整える
- 権限や能力があると従業員に自覚してもらう
- 従業員を信用し、失敗を許容する
- 人事評価制度を整備する
- エンパワーメントを形骸化させない
- 採用段階で候補者の潜在能力を把握しておく
それぞれ下記で解説します。
権限を委譲する範囲を明確にする
エンパワーメントを成功させるためには権利を委譲する範囲を明確に定めることが重要です。
「何でも好きにやって良いよ」というのは、権限移譲ではなく放任です。
また、いきなり大きな権限を与えれば、取り返しのつかない損失と従業員の挫折で終わる恐れもあります。
どのような権限をどこまで与えるのか、どこからは上司の判断を必要になるのか明確に定めることが重要です。
具体的な例を下記に挙げます。
- 部下の育成はすべて任せる
- 経営方針・計画については上司が担当する
- 担当顧客のフォローはすべて任せる など
判断基準を明確にする
権限移譲後に上司と部下、または従業員間で判断基準や方向性にズレが生じることもあります。
この状態を放置すると、間違った判断をしてしまい。重大な損失や信頼の喪失、組織の生産性の低下につながる恐れがあります。
例えば、ある従業員は品質重視である一方、別の従業員はスピード重視であるといった場合、連携が難しくなる恐れがあります。
権限を委譲する際は判断基準を明確にし、事業方針に対して共通認識を持つようにすることが重要です。
報連相を徹底し、支援環境を整える
「権限移譲をしたから口を出さないでほしい」「権限移譲をしたからあとは任せた」では単なる丸投げです。
権限移譲を行ったら、報告義務を設定し、決められた範囲で適切に権限を行使しているかどうかのチェック体制を整えましょう。
また、常に従業員から相談や連絡を受けられるように支援環境を整えておくことも重要です。
権限や能力があると従業員に自覚してもらう

エンパワーメントでは、従業員自身に「権限や能力がある」と自覚してもらうことが必要です。
権限を委譲したとしても、従業員自身が自信を持てなかったり、不安を抱えていたりすれば、十分な効果が得られません。
従業員の心の壁を取り除き、前向きに取り組めるように促すこともエンパワーメントを成功させるポイントです。
従業員を信用し、失敗を許容する
従業員を信用し、失敗を許容することもエンパワーメントの成功のポイントです。
エンパワーメント導入直後は、想定外のミスを起こす従業員が出てくるかもしれません。
しかし、従業員は慣れない環境のなか、成功へ導こうと頑張っているのです。
失敗を責めてばかりいると、モチベーションが低下したり、従業員が潰れてしまう恐れがあります。
また、失敗を責められることで、従業員が報告や相談をしにくくなり、問題を隠蔽したり、大きな失敗につながる可能性もあります。
失敗をしたときは責めるのではなく、なぜ失敗をしたのか、どのように対処すればよかったかをアドバイスすることが重要です。
これを繰り返すことで、困難に立ち向かい、課題解決に導いたという成功体験を積むことができるのです。
人事評価制度を整備する
「責任は上司が負う」とはいえ、権限移譲によって従業員には一定程度の責任が課されます。
そのため、権限を委譲されることで心理的な負担を感じ、モチベーションが上がらないこともあります。
権限委譲を行う際は、従業員の特性や潜在能力を見極めることはもちろん、人事評価制度を整え、権限移譲によって実践した結果が評価につながる仕組みを整えることも重要です。
エンパワーメントを形骸化させない
エンパワーメントを導入したものの、いつの間にか形骸化していたということもあります。
主な原因は、エンパワーメントを推進する風土作りが整っていないというケースが多いです。
形骸化を防止するためには、エンパワーメントの目的や従業員にとってどのようなメリットがあるのかを周知徹底することが重要です。
また、どれだけ周知徹底しても、時間が経てば従業員の記憶が薄れることもあります。
権限移譲によって企業に貢献した従業員に報酬を与えるなど、人事評価制度を整えることはモチベーション向上だけでなく、エンパワーメントの形骸化防止の意味でも効果的です。
採用段階で候補者の潜在能力を把握しておく
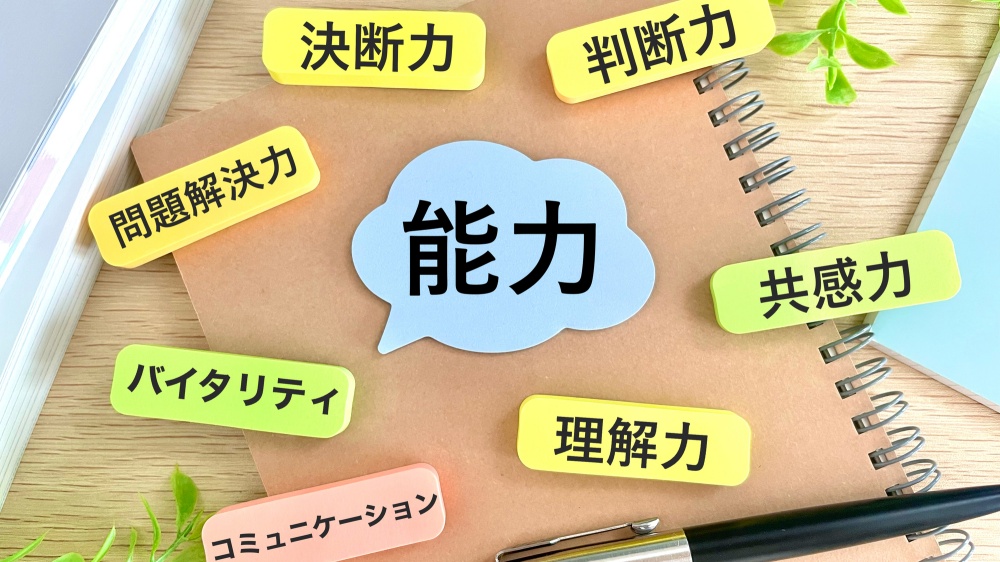
ここまで説明したとおり、エンパワーメントでは、従業員の特性や潜在能力を見極め、適切に権限委譲を行うことが重要です。
VUCA時代を生き抜き、次世代リーダーを育成するためにも、従業員の特性と潜在能力を把握しておくことが重要です。
特に中途入社社員の場合、入社後すぐに権限移譲を予定しているケースもあります。
しかし、入社直後は従業員についての情報が少なく、応募時の提出書類や面接での評価で判断することがほとんどです。
もし、入社した人材が経歴詐称をしているなど権限移譲に値しない人材であった場合、権限移譲によって大きなトラブルに発展する恐れもあります。
エンパワーメントを成功させるためにも、採用前にバックグラウンドチェックを行い、経歴に虚偽がないかを確認することが重要です。
リファレンスチェックで前職での実績や働きぶり、問題行動の有無を確認しておくとより情報精度が高まるため、おすすめです。
まとめ
権限移譲するだけでは、ただの丸投げになってしまいます。
エンパワーメントを成功させるためには従業員を信用し、支援環境を整えることが重要です。
なお、エンパワーメントでは権限移譲する従業員の特性や潜在能力を正確に把握することも大切です。
特に入社直後に権限移譲を予定している場合、採用前にバックグラウンドチェックやリファレンスチェックを行い、候補者の適性を見極めておくことをおすすめします。
VUCA時代を生き抜くためにも、ここでご紹介した内容を参考に、エンパワーメントを効果的に実践していきましょう。

