アセスメント採用とは?メリット・デメリット、成功のポイントを解説
2025.11.10

企業の人事採用担当者にとって、採用ミスマッチの低減や定着率向上は重要課題です。
しかし、従来の書類と面接だけの採用は面接官の主観や先入観に左右されやすく、候補者の適切な見極めが難しいのが現状です。
近年、これらの課題解決のために導入を進める企業が増えているのがアセスメント採用です。
本記事では、アセスメント採用の基礎知識から具体的な実施方法、成功に導くためのポイントまで詳しく解説します。
アセスメントとは
アセスメント(Assessment)とは、直訳すると「評価」「査定」「見積もり」といった意味を持ちます。
アセスメントは様々な分野で用いられており、客観的なデータや基準に基づいて物事を多角的に評価することを目的に使用されています。
人事採用分野におけるアセスメントは、個人の能力、適性、性格、スキルなどを客観的な基準に基づいて測定し、評価することを指します。
これは人材アセスメントとも呼ばれます。
人材アセスメントは採用活動だけでなく、人材育成や組織開発、人事評価など幅広い場面で用いられています。
アセスメント採用とは
アセスメント採用とは、人材アセスメントを利用して候補者の情報を客観的に評価して判断する採用手法です。
候補者の知識やスキルといった表面的なものだけでなく、潜在能力や性格特性、行動特性、職務適性、企業文化との適合性などを客観的に測定し、採用の判断材料とします。
これにより、採用担当者の主観や固定概念を排除し、客観的なデータに基づいた、精度の高い採用を実現することを目指すことができます。
アセスメント採用が注目される背景
近年、アセスメント採用が人事採用担当者の間で注目される背景には、以下のような社会的な変化や課題があります。
- 労働人口の減少
- 中途採用の難度の高まり
- 多様な働き方への対応
それぞれについて下記で解説します。
労働人口の減少
少子高齢化に伴う労働人口の減少は、企業間の人材獲得競争を激化させています。
限られた人材のなかから、自社で貢献できる人材を如何に効率的かつ確実に見極めるかが企業の継続的な成長のための課題となっています。
従来の面接官の主観に頼った採用手法ではミスマッチや早期離職のリスクが高くなります。
このような背景から、より精度の高い採用手法が求められるようになりました。
中途採用の難易度の高まり
キャリア志向の多様化や人材の流動化が活発化していることで、中途採用の難易度が高まっています。
また、中途採用者は前職での働き方や仕事の進め方が染み付いており、新しい環境に適応できないケースもあります。
そのため、即戦力としてのスキルや経験だけでなく、入社後の組織への定着や活躍を見越した、より深いレベルでの適性判断が求められるようになりました。
多様な働き方への対応
近年、テレワークや時短勤務など、多様な働き方が浸透し、労働環境が大きく変化しました。
このような状況のなか、書類選考と面接といった従来の選考手法だけでは測れない、自律性やコミュニケーション能力といった非認知能力の重要性が増しています。
アセスメント採用は、これらの内面的な要素を客観的に評価する手段として期待されています。
アセスメント採用が向いている企業の特徴

アセスメント採用は次のような課題を抱える企業に特に有効な解決策となり得ます。
- 離職率が高い
- 採用ミスマッチが多い
人材の採用にはコストがかかります。
そのため、早期離職や離職率の高さは企業にとって大きな損失となります。
早期離職の原因のひとつに採用ミスマッチがあるといわれています。
採用ミスマッチによる早期離職のパターンの例には以下のようなものがあります。
- 入社後に理想と現実のギャップにショックを受けて離職する
- 候補者の適性に合わない配置をしてしまい、新入社員が自分の能力を発揮できない、やりがいを感じられないなどの理由で離職する
上記の場合、アセスメント採用を行い、候補者のスキルや適性を客観的に把握することでミスマッチの改善に役立ちます。
また、職務への適性や企業文化への適合性を事前に評価することで、定着率の高い人材を採用できる可能性が高まります。
アセスメント採用の代表的なツール
アセスメント採用に用いられるツールには様々な種類がありますが、代表的なものは次の3つになります。
- 適性検査
- 360度評価
- アセスメント研修
それぞれについて下記で解説します。
適性検査
適性検査とは、応募者の性格、意欲、能力などを客観的に測定するツールです。
主に性格検査と能力検査の二つに分かれており、採用試験や昇進試験、配属検討時など様々な場面で用いられることが多いツールです。
採用活動においては、自社が求める採用基準を満たしているかどうか、または満たす可能性があるかを判断するために用いられます。
Webテストと筆記テストの形式があり、短時間で多くの候補者のデータを収集・分析することができます。
なお、よく耳にすることが多いSPIは、リクルート社が開発したテストで、適性検査の種類のひとつになります。
360度評価
360度評価とは、候補者を囲む、上司や同僚、部下など、複数の違った立場の視点から候補者を評価する手法です。
複数の視点で評価することで、多面的で客観的な評価を行うことができます。
アセスメント研修(グループワーク・シミュレーション)
アセスメント研修とは、ケーススタディやロールプレイング、グループワークなどを通じ、候補者のスキルや特性などを客観的に評価するプログラムです。
特にマネジメント職やリーダー候補の採用・選抜、適材適所の人材配置の際に有効です。
採用活動だけでなく、育成を兼ねて用いられることもあります。
アセスメントツールの選び方

アセスメント採用を導入する際はコストやリソースなどを総合的に鑑み、自社に合ったツールを選定することが大切です。
ツールを選定する際は以下のポイントに留意して選定すると良いでしょう。
- 導入目的と自社のニーズに合ったツールを選ぶ
- 測定したい項目や領域の情報を提供できるツールを選ぶ
- 予算とのバランスが取れたツールを選定する
- 信頼性の高いツールを選ぶ
アセスメント採用のメリット
アセスメント採用を導入することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 採用ミスマッチの低減
- 定着率向上
- 採用者のキャリア形成に役立つ
- 隠れた人材を発掘につながる
それぞれについて下記で解説します。
採用ミスマッチの低減
アセスメント採用は客観的なデータに基づき、候補者の特性や企業文化への適合性を評価するため、ミスマッチの低減につながります。
また、アセスメントで気になる点を洗い出し、それを面接で掘り下げていくことで、面接の効率化と採用精度の向上にもつながります。
定着率向上
アセスメント採用により、候補者の能力や適性を事前に把握できれば、適材適所の人員配置が実現できます。
これにより、従業員の能力や特性を存分に発揮でき、エンゲージメントが高まり、定着率向上に繋がります。
採用者のキャリア形成に役立つ
アセスメント採用で候補者の強みや弱みをデータ化すれば、その結果を配属先決定や入社後の育成計画を立てる際にも活用できます。
従業員自身も自分の強みと弱みを把握でき、自分のキャリアプランについて考えるきっかけとなり、自発的なキャリア形成を促すことにつながります。
隠れた人材の発掘につながる
アセスメント採用は従来の書類選考や面接では見落とされやすい潜在的な能力や特徴、行動特性を持つ人材を発掘できる可能性があります。
また、採用前に既存従業員にアセスメントを受けてもらうことで、既存従業員の潜在的な能力や特徴も発掘でき、適材適所の人材配置がしやすくなります。
アセスメントで潜在能力が発掘されれば、入社後の育成で引き出すこともできるため、人材育成にも有効です。
アセスメント採用のデメリット
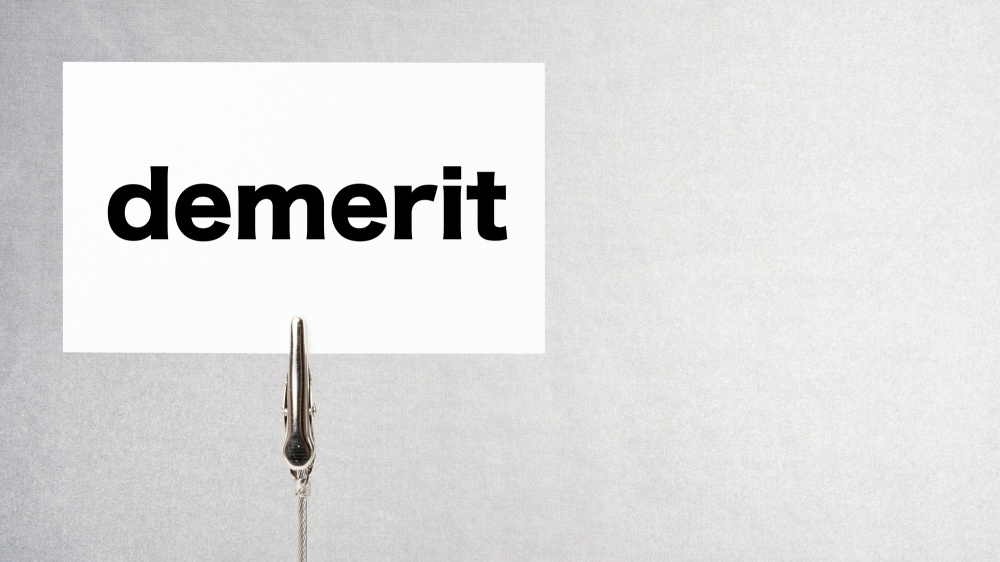
多くのメリットがあるアセスメント採用ですが、次のようなデメリットも存在します。
- 採用コストがかかる
- 採用担当者の負担が増える
- 選考に時間がかかる恐れがある
それぞれについて下記で解説します。
採用コストがかかる
アセスメント採用は専用のツールを導入したうえで採用活動を行います。
アセスメントツールの導入や利用には費用がかかります。
また、外部機関への委託費用やツールの選定・分析にかかる社内コストも考慮する必要があります。
そのため、一人あたりの採用コストが増大する可能性があります。
採用担当者の負担が増える
アセスメント採用は、従来の採用手法と比べて採用担当者の作業や負担が増えます。
アセスメント採用の導入によって採用担当者に発生する作業には次のようなものがあります。
- 測定項目の選定
- アセスメントツールの選定
- 面接や採用判断に活用・分析するための技能習得
- 既存従業員への実施・分析
- 採用プロセスの整備
- 候補者への実施・分析
- 外部委託先とのやりとり など
このように、アセスメント採用の導入には採用担当者の負担が増大します。
リソースが不足している場合は採用活動全体に影響をおよぼす恐れがあります。
選考に時間がかかる恐れがある
アセスメント採用は従来の採用手法と比べて選考プロセスが長くなるため、候補者の離脱を招く恐れがあります。
また、社内のリソースが不足している場合はさらに採用活動が長くなる恐れがあります。
アセスメント採用を導入する際はリソースの確保とプロセス全体の効率化を意識する必要があります。
アセスメント採用の実施方法

アセスメント採用を効果的に実施するための手順は以下の通りです。
- 導入目的を明確にする
- 評価項目を設定する
- アセスメントツールを選定する
- 既存従業員でアセスメントを実施する
- 選考プロセスへ組み込む
- アセスメント採用を実行する
- アセスメント採用の振り返りを行う
それぞれ、順を追って解説します。
導入目的を明確にする
まずはアセスメント採用を導入する目的を明確にし、社内で共有します。
目標が曖昧なままだと期待した成果が得られません。
また、目的が定まっていなければ、適切なツールを選ぶこともできません。
自社の課題を抽出し、それを解決するための目標を具体的に設定します。
自社の課題を抽出する際は現場にヒアリングしたり、事業計画と照らし合わせたりすることも重要です。
アセスメント採用の導入目的の例には以下のようなものがあります。
| 課題 | 目的 |
|---|---|
| 採用ミスマッチが多い | ミスマッチを減らす |
| 早期離職が多い | 入社後3年以内の離職率半減 |
| 〇〇職・ポジションが足りない | 特定職種の人材確保 |
評価項目を設定する
評価項目を定めないままツールを選んでしまうと、求めるデータが得られない可能性があります。
そのため、導入目的を達成するために評価すべき具体的な項目をツール選定前に定義します。
このとき、現場と採用部門が連携し、企業文化や労働環境も踏まえたうえで、候補者に求める能力や特性を定義します。
能力やスキルについては、以下のように具体的にどのような能力をどこまで求めるかまで決めておきましょう。
- 論理的思考力
- コミュニケーション能力
- ストレス耐性
- リーダーシップ など
候補者の特性については、仕事における価値観や人間性などを定義します。
項目を定義する際は優先順位も併せて定義しておくと、判断がスムーズになります。
アセスメントツールを選定する
目的と評価項目に合致し、信頼性・妥当性の高いアセスメントツールを選定します。
費用対効果や、自社のシステムとの連携やリソースなども考慮します。
既存従業員でアセスメントを実施する
実際の採用プロセスで導入する前に、社内のハイパフォーマーや平均的な従業員に対して、同じアセスメントを実施します。
こうしておくことで、選択したアセスメントが適切かどうかや、自社で活躍する人材の基準値を把握することができます。
選考プロセスへ組み込む
選定したツールを選考プロセスの適切な段階に組み込みます。
なお、一般的には一次面接前に実施することが多いです。
一方、スクリーニングが目的であればエントリー時、コストを抑えるならある程度人数が絞られた最終選考前に実施するのも良いでしょう。
アセスメント採用を実行する
候補者に適切に情報提供をしたうえで、設定した評価項目に沿ってアセスメント採用を実施します。
アセスメント結果と面接でのやり取りを照らし合わせ、矛盾がないかを確認し、最終判断に活用します。
アセスメント採用の振り返りを行う
アセスメント採用の振り返りを行うことも大切です。
最初に設定した目標が達成できているか、課題解決につながっているかを分析しましょう。
採用した人材の入社後の活躍度や定着率を追跡し、アセスメントの結果と照らし合わせて検証すると採用精度をアップデートしやすくなります。
アセスメント採用を成功させるためのポイント

アセスメント採用を採用力の向上に繋げるためのポイントには以下のようなものがあります。
- 採用基準を明確にしておく
- 定期的な見直しを行う
- 多角的な視点で評価する
- バックグラウンドチェック・リファレンスチェックを併用する
それぞれについて下記で解説します。
採用基準を明確にしておく
アセスメント採用では、候補者が「自分を良く見せたい」と考え、多少「盛って」回答してくる可能性があります。
そのため、実際より適合性が高い結果が出てしまう可能性があります。
これを踏まえ、採用基準の基準値を設け、「どのラインで合否とするのか」まで決めておくことが重要です。
定期的な見直しを行う
労働市場や企業の求める人材像は常に変化します。
採用基準や評価項目、ツールの有効性などを定期的に見直し、最適化を図りましょう。
面接結果とアセスメント結果の間の大きな乖離が頻繁に見られる場合は評価基準や面接プロセスの見直しも行いましょう。
多角的な視点で評価する
アセスメント結果はあくまで採用判断の材料のひとつです。
アセスメント結果を妄信してはいけません。
面接でのやり取りや印象、候補者のスキルや経験と併せて、多角的な視点で総合的に評価することが重要です。
バックグラウンドチェック・リファレンスチェックを併用する
アセスメントは候補者の潜在能力を測るものです。
それに対し、バックグラウンドチェックは候補者の経歴やスキルに虚偽がないかを確認します。
また、リファレンスチェックは、応募者の経歴や実務能力を第三者からの客観的な評価から確認できます。
前述のとおり、アセスメントでも面接でも候補者が自分の経歴を「盛る」可能性があります。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックをアセスメント採用と併用することで候補者の情報を補完することができます。
こうすることで、候補者の人物像を立体的に捉え、採用精度をさらに高めることができます。
まとめ
アセスメント採用は、データに基づいた客観的な評価を通じて、採用ミスマッチを減らし、企業の競争力を高める強力な手法です。
導入にあたっては、目的の明確化や適切なツールの選定、そして運用後の継続的な改善が成功の鍵となります。
ただし、アセスメント採用はあくまで判断材料のひとつです。アセスメント結果だけで判断するのではなく、他の採用手法と組み合わせて多角的に評価することが大切です。
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを併用することで、候補者の情報を補完でき、採用精度を高めることができます。
レキシルは経験豊富な調査会社のクオリティをリーズナブルな価格でご提供しています。
アセスメント採用の導入をお考えの方、採用ミスマッチでお困りの採用担当の方はぜひご検討ください。

